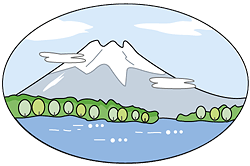 冬将軍が足早にやって来た。 冬将軍が足早にやって来た。
そして、南関東だけ、例の如く快晴そのもの。冬将軍と戦っている人たちには申し訳ないくらいである。
と言いつつ、この快晴、富士見山行でしょうと、出かけるZIOめであります。
そして、取り敢えずの場所は山中湖を見下ろせる三国峠へ、このところ通い慣れた道になりました。
早速、カヤト広がる鉄砲木ノ頭へ。予想通りの大パノラマ、中腹まで雪化粧した富士山はやはり秀麗です。
そして右肩に連なる南アルプスの白き峰々、空の藍に映えて何時までも見飽きることがありません。
これだけではもの足りません。高指山まで歩いて見ることにしました。
冬木立のトンネルが好ましい。風無く陽ざしある冬木立の径は光のプロムナード、愉しい限りです。
西丹沢へ抜ける路をチェックしながら、まもなく高指山に、今日はこの辺りまで。
もっと先に行きたいところです。菰釣山、御正体山がおいでおいでしてますが、今日はここまで、心弾む山歩きでした。(12/15) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
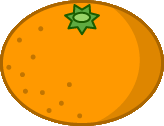 松田山はミカン山、そしてミニ鉄道を敷設しているハーブ園、付き添いはそこまで、ここで解放とか、喜んで! 松田山はミカン山、そしてミニ鉄道を敷設しているハーブ園、付き添いはそこまで、ここで解放とか、喜んで!
まずは、松田ハーブ園から最明寺史跡公園まで歩いてみる。みかん畑抜ける愉しい道である。
小一時間で公園に。桜の季節は大賑わいなのだとか。私もその季節、やって来たいものである。
尾根上に上がるとそこを虫沢古道がはしっている。高松山へ通じているとか、導かれる如く進路を高松山へ。
道すがら、今は閉鎖された高松分校を見たりしながらの愉しい山歩きでした。
富士山展望の山、高松山は、今日も幾人かがランチ中。
私も倣って、ささやかなランチをとることに、富士に雲が纏わりついてきたけれどもそれもまた一興。
そして、山北駅目指して、駆け下ったのでした。この路、近年整備したようで、とても歩きやすい路でした。(12/14) |
 |
 |
 |
| ミカン山からの箱根 |
最明寺史跡公園の桜の古木 |
虫沢古道 |
 |
 |
 |
| 光る相模湾 |
旧高松分校 |
高松山山頂、富士山は雲の中 |
 |
 |
 |
| 整備された登山道 |
ビリ堂の馬頭観音 |
東名高速を見下ろしながら |
 今週は小田原が発進基地に。 今週は小田原が発進基地に。
取り敢えず隙を見てお散歩でも、と秦野辺りを。
以前古墳を探して水無川沿いを歩き、東田原ふるさと公園に駐車場もある事を知っていたので、そこを起点として歩き始める。
そばに源実朝公御首塚のあるところである。
近くの波多野城趾に寄って見る。空堀跡がらしく思える程度の学校横の遺跡でありました。
そこから、高取山へ。途中そば屋さんがありまして、ちょっと昼飯には早いけど寄って見ることにしました。
ざると蕎麦がきを食してお腹いっぱい、さて腹ごなしに歩き始めましょう。
ゴルフ場のフェンス沿いに路がありました。ロストボールが転がっています。けれどZIOめには無縁、無視。
まもなく弘法山からの大山道に合流。このまま大山に行きたい衝動に駆られる。けど3時頃まで戻って来てのリクエスト、後日の楽しみに取っときましょう。
まもなく高取山山頂。NHKの中継基地がありました。木間から伊勢原市街と海が見えてました。
寺山へ下るルートを選択、まもなくゴルフ場に突入、ゴルファーを横目にスタコラサッサ、カート道を急いで通り抜けました。
そしてふるさと公園までのんびりと、後ろには大山やそこに至る大山道の山並みが優しく見守っていました(12/12) |
 |
 |
 |
| 源実朝公御首塚 |
波多野城址 |
大山道 |
 |
 |
 |
| 高取山山頂 |
ゴルフ場からの大山 |
高取山遠望 |
 山のネット情報は紅葉便りで一杯。 山のネット情報は紅葉便りで一杯。
花の命は短くて、じゃないけど紅葉の見ごろも短くて、あっという間に色がくすみ、落葉してしまう。
と言う事で、今日も行ってきました。
起点は八丁橋。オロセ尾根に取り付き、篶坂ノ丸を目指します。
植林帯を過ぎると、彩が一変、紅葉シーズンに間に合いました。イロハモミジであろうか、朝日に映えて深紅に輝いて迎えてくれます。
後は、穏やかな傾斜をゆっくり、ゆっくり上を目指して歩進めます。
もちろん、途中みちくさばっかり、下手な鉄砲も数打ちゃ当る式にデジカメのシャッターを止せばいいのに押してしまいます。
(帰って反省しきり、思った通りの画像なぞあったためしがないのですから。それでも、その時の感覚が大事大事と言い聞かせているZIOめであります。)
着いた篶坂ノ丸はすっかり木立は葉を落とし冬模様、それもまたいい景色です。
更に上へ。ウトウの頭の手作り表示板の無事を確認。この辺り、何度か路を外れかかった箇所、慎重に歩を進めます。
モノレールの軌道が出てくると一安心、長沢背稜の縦走路までは一頭足、水を補給して一呼吸、緊張感を緩めて歩き出します。
タワ尾根ノ頭はパス、風のない日はランチに絶好の場所、ヘリポートに出て展望ランチです。
広角レンズ装着中につき望遠画像を得られないのが残念、雪を頂いた北アルプスの山並みが見て取れます。
目を転ずれば、奥多摩のランドマーク、大岳山が目に入る。もちろん日本のランドマーク、富士山も輝いていました。
熱めの珈琲を片手に至福の時間、今日はこの感じを味わうために来たようなもの、45分程、時間空間を独り占め、満足でした。
さて、腰をあげましょう。尾根伝いに水松山へ。
すっかり葉を落とし冬木立の水松山、間もなくやってくる冬、その備えが辺りに充満している為なのでしょうか、清々しさを感じさせてくれます。
天祖山を目指して下り始めます。雲取山への縦走路との分岐付近で名残りのカラマツの紅葉を見惚れる。
梯子坂ノクビレ辺りもカラマツが同じ感じで、青空によく映えていました。
天祖山の下り、落ち葉で道が解りにくく、心して歩かないとと思っていたら、さほどでもなく、今秋、大部歩かれたんだと実感しました。
下るにつれ色彩が豊かになり、最後まで飽きさせない秋山山行でした。(11/04) |
 |
 |
 |
| 朝日が眩しい(孫惣谷林道) |
のっけから、この赤!(孫惣谷林道) |
オロセ尾根にて |
 |
 |
 |
| この辺りから・・・ |
振り返れば・・・ |
クライマックスへ |
 |
 |
 |
| 重ねて |
そして篶坂ノ丸へ |
ウトウノ頭 |
 |
 |
 |
| 大岳山、御前山 |
天祖山の後ろに富士山 |
両神山、奥に北アの山並みが |
 |
 |
 |
| 水松山 |
縦走路と天祖への分岐 |
天祖山への路 |
 |
 |
 |
| 梯子坂ノクビレ |
天祖山の下り、その1 |
天祖山の下り、その2 |
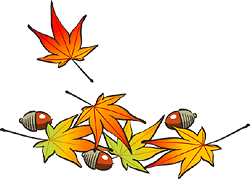 関東の山々にも足早に紅葉シーズンがやって来て、そして立ち去ろうとしている。 関東の山々にも足早に紅葉シーズンがやって来て、そして立ち去ろうとしている。
雲取山周辺でもそうだとか、うかうかしていられません。
そこで、ネット情報を頼りに唐松谷林道~野陣尾根の周回コースを歩いて見ることにしました。
未だリハビリ運転中のZIOめには恐る恐るといったところでしょうか。
故に行動時間は長い方が良い、と言う訳で夜明け前に家を出て圏央道をひとっ走り7時頃には八丁橋たもとに到着。
今日は安定した高気圧に覆われているとか、絶好の登山日和である。焦らずゆっくり確実に歩を進める事にする。
朝日が周囲の山々にあたって美しい。心を浮き立たせ、林道を歩いている段階からすでにMAXに近く、登山口までの一時間が苦にならない程。
いよいよ、つり橋を渡り登山開始。唐松谷ルートを登りに取ったのだが、紅葉の見事さ、石尾根に合流するまで感激しっぱなし、見事でした。
それも独り占めという贅沢さ、推奨してくれたHgさんに感謝です。路もしっかりしていて木橋も補修され、慎重に歩く分には問題なかったです。
そして、石尾根へ。紺碧の空にクリアな富士山がお出迎えです。贅沢にも面白みのない富士山だなと、罰当たりな言を吐いてしまいました。
11:30、予定よりややタイムオーバーして小雲取手前の分岐に到着、ここでランチに。
石尾根からの絶景を愉しみます。ちょっと心臓もドキドキ、雲取山山頂は止めにして、充分に休息してから、富田新道をゆっくり下りることを選択。
唐松の紅葉の盛りが終わっていて、ちょっぴり残念。全体に野陣尾根の紅葉は終わりかけていて、結局ひたすら下っただけでした。
登りの分岐付近が見ごろといったところでしょうか。そして陽ざしのあるうちの林道歩き、これも又愉し、でありました。それでも三時半過ぎから陰り始めます。
八丁橋のゲートの付近で水道局のパトロールの方と立ち話。三月に一度の設備点検とか、暫しの山談義、愉しかったです。(10/29) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
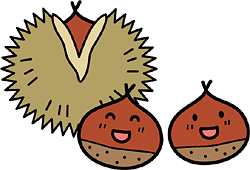 小田原出張も今日で終了、帰りがてらの寄り道、初冠雪が伝えられる富士山でも拝んでからと明神峠に進路を取る。 小田原出張も今日で終了、帰りがてらの寄り道、初冠雪が伝えられる富士山でも拝んでからと明神峠に進路を取る。
着いた峠がガスの中、それも良し、大洞山までの紅葉狩りも悪くはないと、決定!
紅葉狩りには、ちょっと遅すぎたようでしたが、名残りは十分にあり、なにより静かで、思いのほか愉しむ事が出来ました。
3時間弱、のんびり森を逍遥して峠まで下りてくると富士山も顔を出し、ススキ越し目ることが出来、ご満悦のZIOめ。
パノラマ台は相変わらず賑わっておりました。
平野のジェラート屋さんジェラートを食べて、幸せ気分に輪をかけて帰ってきました。(10/27) |
 |
 |
 |
| その 一コマ� ↑↓ |
三国山 |
大洞山 |
 |
 |
 |
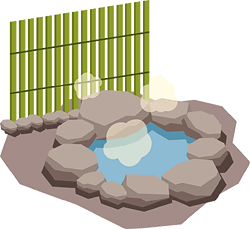 今日は贅沢に湯浜温泉をベースに栗駒の麓をフラフラ、する事にする。 今日は贅沢に湯浜温泉をベースに栗駒の麓をフラフラ、する事にする。
古道の森コースと名付けられた旧仙北街道の支道が好都合にも世界谷内まで通じているので歩いてみることにする。
天気は霧雨模様、朝風呂入って、ゆっくり朝食を頂いて、雨具に身を固めて出発です。
宿自体がブナの森の中にあるので、正に始めから終わりまで、ブナ一色、黄色一色の世界でした。
ちょうど道標の敷設作業中で、その方々と前後しながらの森の逍遥でした。
ただ沢には橋が架かっていないでトラロープづたいの石飛、石を踏み外しでの足濡れは請け合いです。
半分以上いった所に日本最大級のクロベの古木への道案内が、これを見過ごす手はありません。
そちらへ誘導されてしまいます。そしてご対面、なかなか神々しくて感動しました。その周辺には他にも幾本かあって栗駒の森の凄さに感動頻りでありました。
そんな訳でと言い訳して世界谷内まで行かないで戻ってきてしまいました。
路を塞いだ倒木にナメコが生えていたりして、それも収穫、帰って、またまたお風呂にザンブ、極楽極楽の一日でありました。
そうそう、宿から離れた露天風呂も文字道理野趣溢れて結構なものでした。(10/16) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 古道の森 |
 |
 |
 |
| クロベの森の住民 |
 |
 |
 |
| 湯浜温泉 |
旅館への道脇にある露天風呂からの一コマ |
旅館への道脇にある滝 |
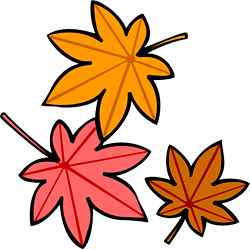 北の方から紅葉」情報がドンドン寄せられているこの頃、ZIOめも何処かへ、と考え、一昨年頓挫した栗駒山に行くことに決定! 北の方から紅葉」情報がドンドン寄せられているこの頃、ZIOめも何処かへ、と考え、一昨年頓挫した栗駒山に行くことに決定!
ただ、台風が立て続けにやって来て、日程調整で二転三転、台風19号の後を追うように出かけてきました。
東北道からの入り易さから一関ICから須川温泉口を目指します。手前の長者原SAで仮眠、登山口に7時前に到着。
晴れ基調なのだが、山頂付近はガスがかかっていて陽ざしが無い、曇りのやや残念な空模様。
それもまた良し、気合をいれて歩き始めます。名残りの原から自然観察路と呼ばれている外周の路を辿ります。
やはり、山頂付近の紅葉は終わっていました。が中腹はまだまだ愉しめる状況でした。
笊森コースとの出会いでは、こちらも静かでいいよ、と言われてるみたいで心が動きました。
東栗駒コースとの出会い辺りから路の両脇が笹となり視界が開け、山頂までもう一息。
10時過ぎに山頂へ。やはり賑わっておりました。いわかがみ平から一時間半、当然ですね(そういう自分も里帰りの折、子供と駆け足で登った昔がありましたっけ)。
ここで早めのランチ。雲の切れるのを待ちます。そして鳥海山までは見えないものの展望が広がり心ゆくまで楽しんだのでした。
さて、それから秣岳経由で下りることにする。このコース、秣岳までちょっとした稜線散歩、展望良し、草原有りで大いに満足しました。
栗駒山の主峰の稜線を眺めることが出来、見下ろせば須川湖が紅葉の中の紺碧の雫のような様は、至福の一時でありました。
そして花の季節にまた訪れたいと強く思ってしまいました。
そんなこんなで、夕暮れ近い3:30頃栗駒道路に降り立ち、急ぎ足で舗装道路を須川温泉まで戻ったのでした。
それと、今日のお楽しみは、もう一つ、宿を「ランプの宿」湯浜温泉三浦旅館に予約、それも二泊。
陽の落ちた頃、宿に到着。
風呂良し、食事良し、宿の人良し。その日、満足感一杯で(もちろん、ビールも入れて)白河夜船の人となりました。(10/15) |
 |
 |
 |
| 名残ケ原 |
名残りの紅葉 自然観察路 |
 |
 |
 |
| 山頂へもう一息 |
振り返れば、笊森方面 |
そして山頂 |
 |
 |
 |
| 宮城・花山側 |
須川温泉を俯瞰 |
秣岳コースより振り返る |
 |
 |
 |
| しろがね草原 |
秣岳より栗駒山 |
須川湖 |
 駄賃がてらの山歩き、第3弾、やはり丹沢に足を踏み入れて見ますか、と言う事で鍋割山へ。 駄賃がてらの山歩き、第3弾、やはり丹沢に足を踏み入れて見ますか、と言う事で鍋割山へ。
お馴染み寄へ。そこの駐車場に車を停めさせてもらって、ここから鍋割山をめざします。
なかなか桜の季節に来ようと思って実現していない土佐原集落を垣間見ながら茶畑を越え山に足を踏み入れます。
そんな表現がピッタリ、獣除けのゲートをくぐります。
以前通った時はこのゲートが枯葉に埋もれていて見逃し通り過ぎ、引き返してゲートを掘り出して開けて通過した記憶がありました。
それに比べると今回は表示板もできて、解りやすく整備されていてビックリ、県民の森までの不安な路も解消、快適な登山道になっておりました。
そんな訳でサクサクと歩け鍋割山へ思ったより楽に到達することが出来ました。
10時ちょっと前に出たのだけれど、ちょうど1時頃に到着、みんな”鍋焼きうどん”を食べている、やはりご挨拶代りに食べることにしましょう。
かすかに見えていた富士山も雲の中、もう、下るしかないのだから。
並んで食べている人と、ひとしきり鍋焼きうどん談義、いや小屋番談義をして、帰路に着きます。
もと来た道を、早めになれど慎重に下ります。ここの所、下りに軽く足を滑らせることが多いのです。
4時頃、寄に立ち帰ることができました。
とりたてて景色よかったわけでも、花が沢山あった訳でもないけど、無事でなにより、目出度し目出度し、でありました。(10/10) |
 |
 |
 |
| 土佐原集落最上部の茶畑 |
鹿除けゲート |
くぬぎ山 |
 |
 |
 |
| 頭を雲の上に出し~♬ |
鍋焼きうどん、頂きま~す♡ |
土佐原集落 |
 |
 |
 |
| モリイバラ |
リンドウ |
ヤマトリカブト |
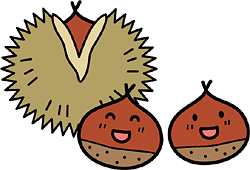 その駄賃がてらの山歩き、その第2弾は、曽我の地から見ると子抱富士のように見える矢倉岳へ。 その駄賃がてらの山歩き、その第2弾は、曽我の地から見ると子抱富士のように見える矢倉岳へ。
地蔵堂からの周回コースをとってみることにする。
地蔵堂でご挨拶して道を横切り茶畑の縁を登っていく。
やがて、矢倉沢に下りて渡渉。そう、橋が無いんですね。メジャーなルートなので少しビックリ。
靴を脱いで渡ることに。増水時は回避が妥当かも。
最初で気合を入れられたが、後は支障なく路もしっかりしていて、ゆっくり歩を進めて行く。
植林帯をいく、やや面白みに欠けるルートではある。高圧鉄塔に沿いながら高度を上げ、万葉公園からの路と合わされば、もう一息である。
よって、花も少な目ながら、セキヤノアキチョウジやツリフネソウが目を愉しませてくれる。
そして山頂へ。何やら立派な望遠を抱えたカメラマンが一杯。聞けばサシバの渡りを待ち構えているのだとか。
へぇ~そうなんだ、と暫し一緒に観察。5羽ほどが海側から箱根の山を越えていくのを観ることが出来ました。
それでも、その集団とは肌合いが違っていたので長居は無用、行動食を口にした程度で、帰路に付きました。
帰りのコースは万葉公園に出る手前で急坂を地蔵堂目指してくだる。
土が肌蹴てやや荒れているが、そこを下ってしまえば、渡渉のない歩きやすい路、木々の色づき具合を楽しみながら、地蔵堂到着となりました。
(10/08) |
 |
 |
 |
| 渡渉点 |
中腹で金時山を望む |
ススキ広がる矢倉岳山頂 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| アキノタムラソウ |
ニガクサ? |
セキヤノアキチョウジ |
ツリフネソウ |
ホトトギス |
ソバナ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| アキノキリンソウ |
|
キバナアキギリ |
ノコンギク |
シロヨメナ |
ホソエノアザミ |
”天高く馬肥ゆる秋”と言ったのんびりした風情に浸っていられない今日この頃ではありますが、
運動会シーズンと言う事で、それなりにお呼びがかかったりして、季節の推移は身近にもあったりします。
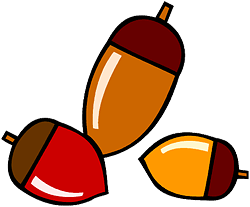 その駄賃がてらの山歩き。その第Ⅰ弾、足慣らしに、曽我丘陵をのんびり歩いて見ることにしました。 その駄賃がてらの山歩き。その第Ⅰ弾、足慣らしに、曽我丘陵をのんびり歩いて見ることにしました。
歩き始めから道端でホトギスが顔を覗かせ、ちょっと嬉しい気分。
ここは果樹山、道の両脇の畑では、未だ熟していないミカンやキュウイがたわわに実をつけて、収穫を待っている。
野生のアケビも今が食べ頃、ちょっと拝借して食べてみる。懐かしいホノ甘さ、少しエグミが口に残る。
目立つ花は、黄色のセンダングサ、赤色のミズヒキ、紫色のアキギリ、アキノタムラソウ、白色のシラヤマギクといった辺りだろうか。
一応、浅間山~不動山~高山と踏んで、見晴らしの良い所で軽くランチして、国府津駅に下りる。
そして麓に点在するお寺や神社、建武の頃の板碑等を見ながらスタート地点に戻ったのでした。(10/07) |
 |
 |
 |
| 小田原・湯河原方向 |
富士は雲の中、金時山をミカンの間から |
国府津から江の島方向 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| アキギリ |
ホトトギス |
アキノタムラソウ |
センダングサ |
カラスウリ |
アケビ |
 本当に、久方ぶりの奥多摩湖である。 本当に、久方ぶりの奥多摩湖である。
どの程度の山が適当か、悩ましい所である。
感覚として、時限爆弾を躰に仕込んだ感じである(それも3発も)。
そして、その起爆スイッチを握り締めながらの山入となる。
だから、我ながら、とても臆病である。
そんな訳での山探し。取り敢えず鷹ノ巣山に、榧ノ木尾根をのんびり、ゆっくりと・・・。
倉戸口から温泉神社に立ち寄って、倉戸山へ。
道端にキバナアキギリが季節の推移を語ってくれている。紅葉も真近である。
高度を上げていくと、植林帯から自然林にかわり、好もしい雰囲気になる。
陽の光が青葉のカエデに差し込み美しい。あと何日経てば、艶やかな衣替えを見せてくれるのやら。
ここの急登、思いのほか大汗をかく。やはり以前とは違うのかな。前回は雪道を路を探しながら通過した記憶がある。
大幅にタイムオーバーで倉戸山に到着。
まぁ、無理をすることはない。穏やかな天気、ここでお茶して、昼寝して帰るのも悪くない。
幸い、なだらかな広場には人っ子一人いない。鷹ノ巣山に行けば、今日あたり人が一杯、好んでその中に入ることはないと自己了解。
そのためのコンロ持参である。いい気分である。これから、こんな山歩きが多くなるのだろう。
お湯を沸かして珈琲淹れて、ランチして小一時間、その場で過ごして、さて下山。女の湯BSに下りてみることにしました。
こちらも登り一方で疲れそう。でも道はしっかりしている。
下ってしまえば、あっと言う間、諦めが早すぎたかなと言う思いを、ほんのちょっと抱きながら奥多摩湖岸歩くZIOめでありました。(9/27)
追記 御嶽山の爆発、驚きました。犠牲になった方々、心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。 |
 |
 |
 |
| キバナアキギリ咲く登山道 |
秋海棠も咲いてました |
好ましい山域風景 |
 |
 |
 |
| 倉戸山で寝っ転がれば |
艶かしい土偶の世界 |
碧き奥多摩湖 |
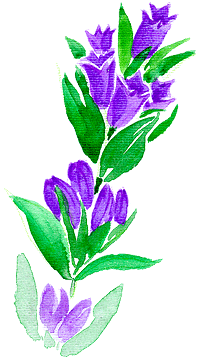 アップが遅れ遅れてアップアップ・・・といったところでしょうか。 アップが遅れ遅れてアップアップ・・・といったところでしょうか。
でも、一応、しないとやはり収まりません。
8月の末、何時もの野草クラブがあって志賀高原をたずねました。
山を登るというよりは、ポイント、ポイントに移動しての観察なので、今一つ達成感がないのが難点ですが、問わないで。
取り敢えず、逢えたて、上手く画像に納められたものを、備忘録を兼ねて、羅列して見ることにしました。
(08/31.09/01.02) |
 |
 |
 |
| 朝もやの中の白樺とミヤマコウゾリナ |
サラシナショウマ咲く湿原 |
白根のヤナギランとアキノキリンソウの競演 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| イワショウブ |
チョウジギク |
サワギキョウ |
エゾシオガマ |
ナガノシロワレモコウ |
エゾアジサイ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| コキンレイカ |
ノコギリソウ |
コウゾリナ |
シラネニンジン |
コバギボウシ |
ミツモトソウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ハクサンフウロ |
マツムシソウ |
キンロバイ |
ヨツバヒヨドリ |
ミヤマノコンギク |
ウメバチソウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ハクサンシャジン |
ソバナ |
シモツケソウ |
マルバタケブキ |
ミズギク |
シラタマノキ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| タチコゴメ |
ミゾソバ |
ツルリンドウ |
ウメガサソウの花後 |
ヤマトリカブトの内部 |
クサフジ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| キツリフネ |
キンミズヒキ |
ツマトリソウの実 |
タケシマランの実 |
コケモモの実 |
オオアワダチソウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ハナイカリ |
クサボタン |
アケボノソウ |
シラヒゲソう |
コバノイチヤクソウ |
ヤマオダマキ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| エゾリンドウ |
オヤマノリンドウ |
ヒメシャクナゲ |
ホツツジ |
コメバオトギリ |
シナノオトギリ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| オミナエシ |
ヤナギタンポポ |
アリノトウグサ |
タニタデ |
オオチドメ |
エゾシロネ |
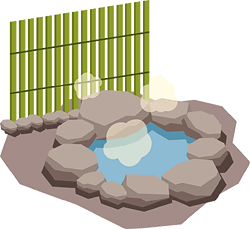 正に夏到来、山に行くなら北アルプス。 正に夏到来、山に行くなら北アルプス。
今年に入って、いろいろあって、やや不安があるものの、思い切って比較的楽な白馬岳を目指す事にしました。
白馬は28年ぶりかもしれない。何とも空恐ろしい年月の隔絶感、その時との体力差を頭に叩き込み、そろりそろり歩を進めることにします。
ルートは蓮華温泉~白馬岳~朝日岳~蓮華温泉の周回ルート、さてどうなりますやら。
幾人ものパーティーに抜かれながら登っていきます。
樹林帯の中、花は少な目だけどオトギリソウ、ゴゼンタチバナ、チダケサシ、ソバナ、タマガワホトトギス、ミヤマアキノキリンソウ・・・とあらわれ、
退屈させない。
天狗の庭で一息、ここで小休止。昨晩の車中泊所、道の駅小谷で買ったおはぎを、お茶を沸かして食す。なかなかの美味でありました。
それから、一時間半以上かけて白馬大池へ。樹林帯から飛び出したらそこはお花畑、白の絨毯はチングルマ、ハクサンイチゲ、イワイチョウ・・・の花のオンパレード。
今年は雪が多かったせいか、残っててくれました。
大いに感激し、少し花を撮って、気持ちを新たに、白馬目指して出発です。
ここからはハイマツ帯、草花を愉しみ、展望を愉しみ、小さなピークをいくつも越しながら、2932㍍まで高度を上げていきます。
予報に反して残念ながら台風の影響かガスが多い。なかなか遠望を得られない。それでも雲間に見える山の風景は日常を飛び越え、何とも気持ちがよい。
そうそう、こんな天気はライチョウのお散歩日和、期待通り何ヶ所かで見かけ、登山者の注目を集めておりました。
ZIOめもお立ち台にいたライチョウくんを激写、ちょっと気分をよくして、歩を進めることが出来ました。
予想タイムより大部遅れての白馬岳山頂への到着でしたが、それも織り込み済み、証拠写真を撮ってから、今日の宿泊所、白馬山荘へ向かったのでした。
小屋は大賑わいで、ややゲンナリ、これも夏山北アの光景と、愉しむ事に。
夜、強い雨。混み合う山小屋の寝床で輾転反側、そしてZIOめの胸の動悸も高鳴ります。
高山のせいか、心筋へ負荷のせいか、ややナーバスに。そして出した結論、明日、朝日岳をあきらめ、往路を下山することにしました。
今年は雪が多く朝日岳の水平道が通行止めとか、次回に(あるのかな?)望みを託すことにしました。
翌日は、心身への重圧もとれ、のんびり、ゆったりの下山。花を愛で、景色を愛で、白馬大池では三脚を取り出しての撮影三昧(内容は聞かないで)
ランチは、コンロを出して「赤いきつね」を食べて、ホットコーヒーを大池を眺めながらすするという、至福の時を過ごしたのでした。
下山後、蓮華温泉には泊まらず姫川温泉に移動、贅沢に国富ホテルに投宿、いい温泉、美味しい食事でありました。(08/03.04) |
 |
 |
 |
| 蓮華温泉から朝日照らす白馬見上げて |
天狗の庭から朝日岳、雪倉岳を |
白馬大池 |
 |
 |
 |
| 白馬大池を後に |
小蓮華越えて |
ピークが見えて |
 |
 |
 |
| ライチョウ |
残念ながらガスの中 |
 |
 |
 |
| タカネナデシコ |
ミヤマアズマギク |
ハクサンイチゲとシナノキンバイ |
 |
 |
 |
| ハクサンフウロ |
エゾシオガマとヨツバシオガマ |
ミヤマダイモンジソウ |
 |
 |
 |
| ミヤマクワガタ |
ユキワリソウ |
チングルマ、イワイチョウ、ハクサンイチゲの競演 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| オトギリソウ |
ヤマブキショウマ |
オタカラコウ |
タマガワホトトギス |
ミヤマコゴメグサ |
ミヤマムラサキ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| チダケサシ |
ヤマハハコ |
メタカラコウ |
ハクサンオミナエシ |
オニアザミ |
ソバナ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ミヤマウイキョウ |
タカネヤハズハハコ |
コマクサ |
ミミナグサ |
イワツメグサ |
ミヤマミミナグサ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| タカネシオガマ |
ミヤマムラサキ |
アオノツガザクラ |
リンネソウ |
イワギキョウ |
チシマギキョウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ムカゴトラノオ |
オオバミゾホウズキ |
イワイチョウ |
イチヤクソウ |
コイチヨウラン |
キソチドリ |
 蒸し暑いですね。もうそろそろ梅雨明けでしょうか。台風を気にしながら山地図を眺めて思案顔。 蒸し暑いですね。もうそろそろ梅雨明けでしょうか。台風を気にしながら山地図を眺めて思案顔。
ところが、かなり突然に信州行きが決定!山が先でなく善光寺行きが事の初め、ならば近くの山を一つと言う事で、斑尾山を歩いてきました。
謂わば信越トレイルをちょこっとばかりかじってきました。
斑尾高原スキー場から出発です。スキー場の刈り払われた道をちょっとそれて朝露をかき分けながらリフトの最終地点辺りまで這い上がります。
道端にはウツボグサ、斜面はヒレアザミ、ヨツバヒヨドリ・・・が生い茂り、その周りをヒョウモンチョウが飛び交ってました。
ヤナギランも咲き始め夏の到来ま近を告げてるかのようでした。
縦走路即ち信越トレイルに出ると深緑に覆われた白樺林が迎えてくれ、その中をトレイルランナーが次々と追い越して行きます。
如何にも斑尾らしい光景です。山頂は展望はなく、大明神岳まで足を延ばすと眼下に野尻湖が広がります。
ただ、山は雲がかかっていて妙高山の先っぽがやっと見えるだけ、ちょっと残念ではありました。
後は、万坂峠を目指して下ります。万坂峠から袴湿原へ、ここからが今日のハイライトかもしれません。
かなり乾燥化した湿原でトキソウが出迎えてくれました。袴岳に登らず赤池へ、ここでランチにします。
一息つき、さて、ここから沼の原湿原を経由して斑尾高原スキー場まで帰らなければなりません。
春ならばミズバショウやリュウキンカが咲き競う沼の原湿原、今はアシが生い茂り花はあまり見当たらない。
ミズチドリがその視線を一手に引き受けている感じである。ひっそりカキランも居たりしてそれなりに楽しめました。
そこからスキー場まではけっこう長かった気がします。
まだらお高原山の家で大休止、信越トレイルの情報を仕入れ今日の宿、タングラムHに向かったのでした。
翌日、雨模様、飯綱山登山を軽く撤回、5月に訪れた乙女平と笹ヶ峰牧場をのぞいて見ることにしました。
かなり地味な花ばかりで、少し盛り上がりに欠けましたが、それも一つの姿、のんびりできました。(07/12.13) |
 |
 |
 |
| アザミに群れるヒョウモンチョウ |
ヤナギランが咲き始めました |
大明神岳から野尻湖を、右上に雲をかぶった妙高 |
 |
 |
 |
| 信越トレイル |
鮮やかハナニガナ |
ウツボグサも負けてはいません |
 |
 |
 |
| トキソウ |
ミズチドリ |
カキラン |
 |
 |
 |
| 乙見湖からの妙高 |
夢見平 |
笹ヶ峰の一コマ |
 |
 |
 |
| オタカラコウ |
エゾノヨツバムグラ |
ズダヤクシュ |
 |
 |
 |
| ショウキラン |
クルマムグラ |
ズダヤクシュの花序 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| コナスビ |
ホタルブクロ |
ギンリョウソウ |
ダイコンソウ |
オカトラノオ |
カタバミ |
 夏を前に天気が落ち着きません。 夏を前に天気が落ち着きません。
山から、やや遠のきつつあるZIOめですが、野の山の花を探して出かけてはおります。
鹿沢休暇村を起点に周辺を、野草観察会の尻っペタにくっ付いてのことですが。
だから、積極的にどのルートを歩いたとかではなく、無知の私が出会って習い覚えた草花を羅列して、自身の再確認の為の記事、
と言ってもいいかもしれません。所詮、このHPはそんなものですけど(^0^;)
ルートとしてはまず車坂峠へ、そして高峰林道を池の平湿原方面へ。途中までですけど、そして休暇村のある鹿沢園地で一日目終了。
二日目は峰の原高原、ここでイチヤクソウの群落に遭遇、ちょっと衝撃と感激!
何故なら秋に紅葉とキノコ料理、冬にはXカントリースキーと訪れていた地にあったのですから。菅平高原自然館も立ち寄って、終了。
三日目、バラキ湖周辺を歩いて帰路に着いたのでした。(06/29.30.07/01) |
 |
 |
 |
| 夏雲思わる高峰高原の一コマ |
レンゲツツジも終盤 |
ヤグルマソウ咲く峰の原スキー場 |
 |
 |
 |
| ベニバナイチヤクソウ三態 |
 |
 |
 |
| スズラン |
ヒメイズイ |
クサノオウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| コイワカガミ |
シャジクソウ |
ヤマスズメノヒユ |
コケモモ |
シロバナヘビイチゴ |
ミツバツチグリ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| マイズルソウ |
ミツバオオレン |
ゴゼンタチバナ |
オオヤマフスマ |
チゴユリ |
ヒメヘビイチゴ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ヒレアザミ |
ツマトリソウ |
ケブカカコソウ |
ホソバイラクサ |
オドリコソウ |
ミゾホウズキ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ニシキウツギ |
ミヤママタタビ |
グンナイフウロ |
サギスゲ |
ウツボグサ |
グンバイヅル |
 |
 |
 |
| ヤマオダマキ |
ヤマホロシ |
キバナノコマノツメ |
 |
 |
 |
| ミヤコグサ |
カラマツソウ |
ニッコウキスゲ |
 |
 |
 |
| アヤメ |
イワハタザオ |
コケイラン |
 |
 |
 |
| ネバリノギラン |
ヤマハタザオ |
バラキ湖とカンボク |
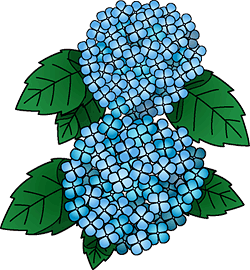 梅雨の晴れ間を狙って日光・社山へ。 梅雨の晴れ間を狙って日光・社山へ。
何故ここか、と言うと、ある事情で札所巡りを始めまして、立木観音で有名な中禅寺に参ることになりました。
ならば後ろの山、半月山、社山巡りは、其の企画にコミコミでしょう、という次第です。
半月山駐車場を起点としました。ところが考えて見るとお寺の駐車場を起点としたほうが楽だったのですね。
それもまた良し。今日は晴れていて展望が抜群、中禅寺湖と日光連山がくっきり見えています。
ある意味、このコースのほうが尾根通し、気持ちの良い路で、正しい選択だったのかもしれません。
花はシロが終わり、ほとんど何も見かけず残念!ただ新緑が、それはそれは、鮮やかでありました。(06/16) |
 |
 |
 |
| 半月山展望台から |
そして行く手、社山を展望、奥に皇海山が |
新緑の瑞々しさと空の蒼と湖の藍 |
 |
 |
 |
| 戦場ヶ原を望む |
社山まで到達した萌え |
山頂シラカバ林越しの中禅寺湖 |
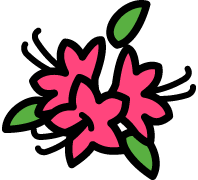 今日の徳仙丈山は全くの観光ハイク、それもまた良しと割り切って躑躅を楽しむことにしました。 今日の徳仙丈山は全くの観光ハイク、それもまた良しと割り切って躑躅を楽しむことにしました。
全山真っ赤を期待して訪れたのでしたが、残念!今年は去年に引き続き花つきが悪いとの事。
ヤマツツジが咲ききらないうちに終わり、レンゲツツジが咲き始めた、そんなタイミングらしい。
タイミングの合うほうが奇跡、十分楽しめるものでした。
それでも、お山は大賑わい。ここは大きく被災した気仙沼の地、良き哉良き哉ではあります。
そして、気仙沼港はまだまだ、という印象でありました。(05/30) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
クルマバソウ |
ニオイタチツボスミレ |
 気にかけていた東北、わが故郷でもある宮城に思い切って出かけて見ることにしました。 気にかけていた東北、わが故郷でもある宮城に思い切って出かけて見ることにしました。
以前から気になっていた徳仙丈山と気仙沼休暇村をドッキング、他人のプランに乗っかって見ることにしたのです。
ところで、それではあまりにもお手軽過ぎ、途中、行きがけの駄賃に、仙台郊外の泉ヶ岳に寄って見ました。
表コースは案に相違して岩混じりの急登、樹林帯なので展望はないが、ニリンソウなど咲いていて苦にはならない。
またシロヤシオの咲いている箇所があり、嬉しがらせる。そんなこんなで退屈せずに頂上まで行き着くことができる。
頂上は展望があまりよくない。が、平らでランチするには最適。少々早めながらランチに、コンロで湯を沸かすことにします。
H珈琲で寛いだらカモシカコースをそそくさと下ります。何せ気仙沼と仙台は結構離れているのです。(05/29) |
 |
 |
 |
| 泉ヶ岳頂上 |
兎平から振り返る |
シロヤシオ |
 |
 |
 |
| マイズルソウが咲き出しました |
ニリンソウとクモ |
シロのアップ |
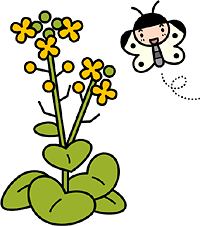 山は何やかやと行きそびれてしまっております。 山は何やかやと行きそびれてしまっております。
そこで、ここに相応しい話題となるとスミレなど野の花の話となるのかなと思いアップしてみました。
行先は戸隠斑尾方面。もちろん自分ひとりではチンプンカンプン、野草観察会の尻ッペタについていったのです。
飯綱原の大谷地湿原・一の鳥苑地が最初の観察地点、素人のZIOの目には鮮やかな黄色のリュウキンカにまず目がいってしまう。
同じく素人受けするミズバショウは終盤、ニリンソウはまだ盛りという感じでした。
もちろん、他にもたくさん、ZIOめが認識できたものを張り付けて見ました。
次の日は、まず、妙高高原のいもり池に。
雪を戴いた妙高が美しく、、花を見る人、鳥を見る人、写生する人と大賑わい。それも肯ける景観ではありました。
花はミツガシワが白の主役を張っていて、ズミが開花までもう一息という感じです。
そして、乙見湖・夢見平へ。ダムの堰堤を通って遊歩道への階段を登ると、残雪がお出迎え、季節が一気に巻戻った感じです。
よって、カタクリがエンゴサクが紫の微笑みで迎えてくれたのです。正に夢見平でした。
県民の森に寄って、この日の予定は終了。後は宿に戻ってビールです。
最終日は戸隠森林植物園を中心に歩いて帰ってまいりました。(05/18-20) |
 |
 |
 |
| ニリンソウ咲く戸隠の小径 |
夢見平はカタクリの花の盛り |
ミズバショウ越しの三田原山 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ニオイタチツボスミレ |
オオタチツボスミレ |
アオイスミレ |
コスミレ |
ミヤマスミレ |
ツボスミレ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ヒナスミレ |
シロバナスミレサイシン |
スミレサイシン |
ヒカゲスミレ |
リュウキンカ |
ヒトリシズカ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ニリンソウ |
センボンヤリ |
ギンラン |
ホソバノアマナ |
クリンユキフデ |
テングクワガタ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| コミヤマカタバミ |
ウスバサイシン |
コシノカンアオイ |
サンカヨウ |
タチカメバソウ |
タケシマラン |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| キクザキイチゲ |
シロバナエンレイソウ |
エンレイソウ |
ミツガシワ |
コキンバイ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ジンヨウイチヤクソウ |
ベニバナイチヤクソウ |
エゾエンゴサク |
ヤマエンゴサク |
フデリンドウ |
ミツバツチグリ |
 久しぶりのアップとなりました。 久しぶりのアップとなりました。
桜がちょうど見ごろを迎えた頃、突然の胸の痛みに耐えかねて~♬、病院に。
恋する乙女でもあるまいに、そう、軽い(?)狭心症でありました。
やはり、患った場所が場所だけに亥年生まれの無鉄砲なZIOめも、お出かけは少々躊躇、一月ばかりの御無沙汰となりました。
季節は桜も終わりヤマツツジの咲くころ、寄居、長瀞辺りが最初のお出かけに向いているのではとチョイス。
R140を走っていると目立つ金尾山を最初のターゲットに設定、行って見ました。
若干早めなれど咲き終えた花弁の見苦しさを思えばと蕾みと花の同居する今の時期が見ごろともいえる。
さて、ここを起点にするにはシックリしない。場所を変えることに、岩根神社に移動、ここから周遊開始。
ミツバツツジの名所、如何かな?と恐る恐る近づくと先週で園は終了、やや残念。
なれど、静かで訪れる人もなくZIOメとしてはGood!社にお参りしてから歩き始めました。
閉園したとはいへ、まだまだツツジは見頃、ちょいと大山祇神社の在る辺りまで失礼、目を愉しませていただきました。
葉原峠まで舗装路をてくてく、尾根道に入ります。この道5/11日外秩父トレイルランのコースになるようです。
ここから、賽神峠までの区間は楽しい路、後半は野草を愛でながら路でした。
釜山神社の手前の見晴らしの良いベンチでランチ。
一服してから、釜山神社にお参り。
登谷山方向に歩いて見るが起点から離れすぎるのを嫌い、戻り奥の院(釜伏山)を目指す。
さすが、奥の院への参道、岩登りの感じを味わえるとは、今日の最大の収穫でありました。
ツツジも沢山、ヤマツツジはこれから、ミツバやシロヤシオは終わっていたが、また来る愉しみができたというもの。
風布まで下りて、さて?舗装道を大回りするのはゲンナリ。みかん山を横切ってショートカット葉原峠まで戻ることにする。
そして、無事起点岩根神社に到着したのでありました。
帰りにかやの湯で入浴、貸し切り状態だったせいもあり、とてもいい湯でした。ごちそうさま。(4/25) |
 |
 |
 |
| 金尾山からの眺望 |
岩根神社 |
ツツジ園の風景 |
 |
 |
 |
| ツツジのトンネルを行く |
山吹の花咲く路 |
釜伏山を望む |
 |
 |
 |
| 釜山神社 |
奥の院(釜伏山) |
駆け上がる新緑 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| タチツボスミレ |
エイザンスミレ |
|
シコクスミレ |
ヒゴスミレ |
アケボノスミレ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ジュウニヒトエ |
キケマン |
イカリソウ |
チゴユリ |
エンレイソウ |
ムラサキケマン |
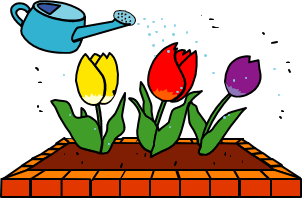 「暑さ寒さも彼岸まで」 「暑さ寒さも彼岸まで」
雪国や北国の方々には申し訳ないけれど、寒かった冬が去り、一気に春の訪れを感じられるここ数日です。
ネット上でもハナネコやスミレの情報が飛び交っています。
なので、尻叩かれますネェ。
そこで立てたルートは寸庭から鉄五郎新道を辿ってイワウチワの様子を見ながら御岳神社にご挨拶をして日の出山にまわり、
今年限りと言われる梅の公園に立ち寄るプランです。
おだやかな陽射しの中、いい気持ちで歩き出します。雪はすっかり無くなっていました。
きれいに枝打ちされた杉林の中を進みます。金比羅神社の参道でもあり、路を整備してくれてるのでしょう。感謝です。
イワウチワはHgさんの報告どおり未だ、開花期は今年は4月ずれ込むのかもしれませんね。そう言えば茨城のお岩山も気配無しと友達が言ってました。
大塚山の下の中継施設の北斜面に雪の名残があって、なかなかいい感じでした。
ここからは雑木林の路、春の陽射しが歩みにリズムを与えてくれ、音痴な私でもスキップしたくなるよううな気分です。
武蔵御嶽神社に近づくと人と出会い始め心が和む。神社にお参りしてから裏手の摂社にもご挨拶。すると御岳山の標高碑、今まで見逃していた!。
今日、初めて御岳山に登頂したのでありました。そこに祀られていたのが大口眞神、ヤマトタケルはともかく自主神の姿を見た気がしました。
そこから日の出山へ。注意書きでは雪による通行注意、でももう大丈夫。大岳山はどんな様子かな、ちょっと気になります。
日の出山山頂は大賑わい。お決まり、年配の(中に若い方も)女性(男性は少数派)グループが東屋を、ベンチを陣取っていました。
風も無く、昼時(11:30分頃)、ここでランチをとることにします。
良く見るとここは山城、石垣が砦の痕跡を残している。武蔵野国を一望に治められる特等地。御岳神社とも尾根路で繋がっている。
古代から何らかの柵や烽火代台があり、戦国時代、北条氏と上杉氏との城獲り合戦の場なのであろう。北条氏の出城作戦の一つだったかもしれない。
等と妄想を逞しくしながら、一路吉野梅郷へ。
病気防除の為、今季限りという梅見を逃すまいと梅見客で大賑わい。それに便乗!珠には祭り気分も悪くない。
下手な写真を撮りまくって、さすがに疲れて日向和田に向かったのでした。(03/24) |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
御嶽神社遠望、冬木立は展望を助ける |
大口眞神と御岳山表示石柱 |
 |
 |
 |
| 日の出山の城址 |
梅の公園 |
 大雪から3週間、もうそろそろ奥多摩に足を踏み入れても良さそうかなと思い立ち、手始めに浅間尾根を歩いてみることにしました。 大雪から3週間、もうそろそろ奥多摩に足を踏み入れても良さそうかなと思い立ち、手始めに浅間尾根を歩いてみることにしました。
桜の季節は如何にも心地良い時坂からのコースの変貌振りを愉しむのも今日の一興です。
集落の雪は、もう殆んど無くなり孤立を伝えられたのも嘘のようでしたが、だからこそ山に入れているのだから当然です。
峠の茶屋を過ぎると案の定雪道となります。トレースはしっかりあり、雪踏み初級編、良いコースです。
ラッセルした人に感謝しつつ快適に森の中を進みます。陽光が射し込み雪面に木立を映しこみ奇麗、うっとり、来てよかったです。
浅間嶺に到着。その名に違わず富士山がクッキリ見えています。小休止、ランチにはちょと早い、先に進みます。
大岳山を横に見ながら、その奥の山の真っ白さに目が行く。長沢背稜の山々であろうか、と言うことは、まだ歩くのは大変という事なのであろう。
人里峠を過ぎ一本松で、ひなたぼっこしながらランチタイム。あったかいコーヒーは休憩感(幸福感)を増幅する。
脇を何人か通り過ぎる。私と逆の下りコースを取る人が多いようだ。
元気が出たのでもう少し先へ進む。気温が上がり、雪がゆるくなって、踏み抜く回数が増えて歩きにくい。
仲の平BS下山口で下る事にする。雪の残るかなりの急斜面、慎重に一歩一歩足の置き場を探していく。
そして檜原街道へ。終点の数馬BSまで行ってバスを待つ事にする。まだ都民の森へのバスは運行を休止しているようだ。
3時発のバスに乗り込み役場前まで戻る。
バスを降りながら、結構な距離をあるいて、結構な運賃料がかかるものだと、思わず今日の行程を振り返ってしまった。(03/08) |
 |
 |
 |
| 雪に映える冬木立を楽しみながら・・・ |
 |
 |
 |
| 奥多摩三山がのびやかに見えます |
正に浅間嶺、雪をかぶった富士が見えてます |
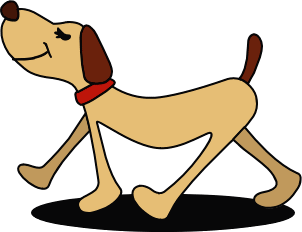 今季、二度目の大雪は山間部に多大な被害をもたらし、当事者の方々にエールを送るばかりのZIOめであります。 今季、二度目の大雪は山間部に多大な被害をもたらし、当事者の方々にエールを送るばかりのZIOめであります。
千葉にいると外環が止まった時点でアウトなのです。そんな訳で道路情報に耳をそばだてておりました。
いつもお呼びで小田原に来たついでに、雪の様子を見に箱根か富士五湖方面でも思ったのだが、
梅咲く曾我丘陵も悪くないと行き先変更、そこを歩いてきました。
この地は大雪の時も箱根止まり、比較的被害が少なく、隣の小山町の孤立が信じられない位でした。
丘陵は果樹園だらけ、よって作業道もあっちこっちに。剪定作業している農家の方とコミュニケーションをとりつつ大井町方向からのんびり入ります。
道端にはオオイヌノフグリやオドリコソウが咲き始め、早春の光を一杯に浴びて気持ちよさげ。
尾根上に出ると丹沢山塊が良く見えてくる。183㍍三角点辺りでは富士山が立ち現れ、その前景として箱根の連山も良く見えている。
まず鉄塔立つ浅間山へ、そこから、この丘陵の最高点327㍍不動山へ。ここは見晴らしが悪く通過、六本松、一本松と過ぎ246m三角点高山に到着。
ちょうどお昼刻、道端に腰掛ランチする事に。
眼下に梅畑、気温が上がり春霞、富士山は姿を隠したものの相模湾と小田原の街見つつ箱根の山並みもと贅沢気分、
コンロを背負ってきた甲斐があったというもの、コンデンスミルクたっぷりのコーヒーを、それはそれは美味しく美味しく頂きました。
国府津出るか、別所梅林に出るか、別所に下り梅林を梯子しながら、出発地点に戻る事にしました。(02/26) |
 |
 |
 |
| 富士山に背を押されて出発 |
黄色の花に目を魅かれます、ミツバツチグリ? |
果樹園の後は丹沢山塊 |
 |
 |
 |
| 梅に富士 |
別所梅林、光は相模湾 |
 今年の雪の量、多いですね。 今年の雪の量、多いですね。
奥多摩辺りでも、かなりの積雪量、果敢にラッセル、撤退の記事を読んで、想像しておりました。
が、やはりムズムズ、そろそろ足の方も良さそうに思え、リハビリ登山と銘打って、六ツ石山に出かけました。
ここならアプローチも短いし、石尾根で雪の感触も味わえて、少しは皆さんのお仲間に入れるかなと考えたしだいです。
案の定、しっかりトレースが出来ていたので、慎重に一歩一歩進みます。
何しろ患部は習慣化し易い「ふくらはぎ」、突発的動作が大いに不安、滑らない、転ばないを第一に足を進めます。
そんな訳で40分程多く時間を費やして頂上に到着したのでありました。
両脇は50cm程の積雪、最初にトレースをつけた人は大変だったろうなと、思いを馳せたのでありました。
風がなかったので、尾根の木の辺りの雪の無い辺りを選んで、アンパンをかじり、お茶で流し込んで、ランチ終了。
後は、とっとと下りて、きょうの行程は終了したのでありました。(02/13) |
 |
 |
 |
| 水根地区から、向に御前山が |
日差しが差し込み、いい雰囲気に |
ハンノ木尾根からのトレースはなし |
 |
 |
 |
| 奥多摩のランドマーク大岳山 |
積雪量50~60㎝あるようです |
山頂、かなり踏まれてました |
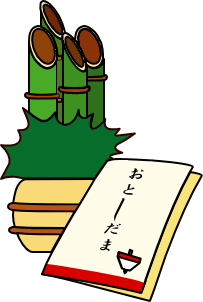 明けましておめでとうございます。 明けましておめでとうございます。
2014年のアップが大幅に遅れまして、一月の晦日に作業している有様であります。
諸事情あり、そして諸事情がなくても、出不精になっていて、ネタ不足が現況です。
一応、遅ればせながら、山も目指したのです。
23日(木)、三つ峠へ。
北登山口から登り始めたのですが、御巣鷹山直前の急登でコムラ辺りがブッチン、と音がしたような気がして、「やっちまったかな」、
そのまま、回り右、戻ってきてしまいました。
病院での診断の結果、「肉離れ」!なんという2014年の出だしであります。
暫くは、皆さんの山報告を、涙目で拝見する事にします。グッスン。(01/23) |
 |
 |
 |
| まだ、元気モードだったのですが |
ここの難所で敢え無く撤退 |
帰りの富士山が奇麗でした |
| |
 |
|

