 そうだ!奈良に行ってみよう。 そうだ!奈良に行ってみよう。
そんな気分になりまして出かけました。
その膝栗毛のつまみ食いはmyブログにゆずるとして、唯一此処にふさわしい話題は「愛宕参り」、愛宕山登山をちょこっと記すことにします。
起点が奈良、で京都縦貫道に入り千代川ICを出たのがいけなかった模様。
西ケ谷ダム経由、柚の里水尾通り抜け、保津峡六丁峠を通って大迂回、やっとのことで清滝に到着したのでありました。
そこからは鳥居をくぐり表参道を丁石、石地蔵に誘われて進めば良いだけです。
展望の利かないのがやや不満なれど、薄暗く参道らしいと言えばその通り、丁石を数え地蔵さんの表情をのぞき込んで歩けば退屈はしません。
これが「千日参り」の日だったりしたら、それはそれは賑やか、上り下りの挨拶してる間についてしまいそうです。
水尾別れでひと息ついて黒門まで辿り着けば、もうそこ、神社手前の石段を詰めればそこは愛宕山頂上でもあります。
先ずは火伏の総鎮守、愛宕神社にお参りします。そして「火廼要慎」の守り札を頂きます。
あとは石段下脇にある休憩所でランチにします。
登り始めは陽が差していたのに陽が陰ってきて結構寒い。休憩所の寒暖計は2℃くらい。やはり標高924㍍の地、風も吹いてきて氷点下の体感です。
ここはホットコーヒーの出番でしょう。それをすすりながらささやかな幸福感を味わいます。
さて、あとは下りるだけ、帰りは月輪寺コースを辿って帰りましょう。
月輪寺の境内を通り抜け、空也滝への分岐もある月輪寺登り口に出れば、舗装路を朝の起点清滝へ進むだけです。
少し拍子抜けの感はありましたが、無事「愛宕参り」を済ませたのでありました。
「火の用心」さっしゃりませ~ぇ。(12/19) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 向かいに見えるは比叡か |
桂川が煙ったなかに |
水尾岐れ |
 |
 |
 |
| 黒門 |
|
|
 |
 |
 |
| 愛宕神社 |
神使猪 |
月輪寺 |
 寒気団が関東南部まで下りてきて、明日は山沿いでは雪となるでしょう。 寒気団が関東南部まで下りてきて、明日は山沿いでは雪となるでしょう。
こんな天気予報を耳にして、「宵のうちに通り過ぎ朝から晴れるでしょう」などとおっしゃられては黙っていられません。
このところ、何だかんだで山への一歩を踏み出せずにいたので、尚更です。
何処へ、やはり雲取山でしょう。
2月以来となりました。
雪はブナ坂手前からちょこっと。ただ、気温が氷点下、下が凍っているので縦走路に出てから軽アイゼンを装着します。
好天を期待しての山行でしたが雲がドンドンでてきて遠望が利かず残念!
それでも今期で営業を終えるという奥多摩小屋を覗いたり、木の間越の浅間山を見ることができたりと、それなりに楽しむことができました。
寒さも体感出来て、ZIOめも冬仕様となりました。(12/13) |
 |
 |
 |
| 来年は2019年ですね |
青空と冬木立、好きです |
富士山は雲の間からちょこっと |
 |
 |
 |
| 奥多摩小屋今期限りとか、名残惜しい |
石尾根 |
避難小屋見えました。もう少し |
 |
 |
 |
| 天気予報ハズレ、富士山見えず |
木の間越に浅間山が |
奥多摩三山が良く見えてます |
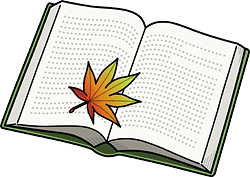 もたもたしているうちに季節がグングン進んで高い山は既に紅葉シーズン終盤。 もたもたしているうちに季節がグングン進んで高い山は既に紅葉シーズン終盤。
未だ良さそうな山は?そんな思いを巡らして辿り着いたお山が三頭山。
小菅側からの三頭山は中々魅力的、間髪決定!行ってみることににしました。
3年前に同じルートを辿っていました。、知ってる路、ゆっくり愉しんで歩くことにしましょう。
オマキ平には先客が数台、東京都水道局の車も、お仕事ご苦労様です。
予想に反してちょっとガスっているけれど、早速登ることにしましょう。
三頭山の北の斜面に当たるため登り始めは陽の光は望めません。もくもくと歩いて向山を目指しましょう。。
予想通り向山に近づき植林帯を抜けると黄葉が待っていてくれました。そしてガスっていた雲間から陽の光も差し込んできて、ナイス!です。
朽ちた展望台と紅葉、そして紺碧の空、絵になりますと、自分の中では妄想が駆け巡ります。
ひとしきりデジカメのシャッターを押しまくって、尾根筋を辿って三頭山を目指します。
このルート、小菅村が力を入れているようで、笹畑ノ峰の手前に笹畑への下山ルート表示板が新しくできていました。
そして鶴峠へのルート合流点まで階段取り付けられていたのにはビックリです。
この縦走路の辺りでは、さすがに木々は葉を落とし冬木立に姿を変えていました。
そして三頭山へ、ポンと飛び出します。そこは、たくさんのハイカーがランチタイム中、誰にも会わなかったので、思わずパチリ。
ガスって来たし、富士山も見えない、早々にランチを切り上げて下りることにしましょう。
多摩湖側に下り、途中から玉川沿いに下ります。
ここからが今日のメーンストリート、チョットだけ時期が遅かったけど、ZIO的には十分な秋の贈り物に出会えることができました。
特にカラマツの黄葉に出会えたこと、小雨かと思うほどのサラサラとした音、それはカラマツの黄金の針の降り注ぐ音。
暫し、佇んで耳を傾けていました。
こうして玉川キャンプ場まで、独り占めの紅葉見物が続き、ずっと私を愉しませてくれたのでした。(11/10) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 鳴子温泉で同級会が終わりまして、天気は全国的に晴、これではこのまま帰れまてん。 鳴子温泉で同級会が終わりまして、天気は全国的に晴、これではこのまま帰れまてん。
もう一つ山を登りたいと思いまして、鳴子周辺の山を物色。
腹案として神室山を考えていたのですが、下山後の宿を確保できず断念。
アクセスの良さと登山時間が限られていることから栗駒山へ行くことにしました。
いろいろありまして須川温泉登山口についたのが11時ごろ、早速支度をして、パンをかじりながら登り始めます。
天気は快晴、惜しむらくは紅葉シーズンは終えつつあるようだったが、登山口に至るまでの真っ盛りの黄葉を目にすることができたことで、良しとしましょう。
やはり人気の山、観光客から登山者まで、幼児から年配者まで、単独からファミリーまで、多くの人とすれ違います。
1時間半程で栗駒山頂上へ、360度の展望です。北方向に見える焼石連峰が近い。
西方向に見える平らな山が船形山か、その右方向は行きたかった神室山の山並み、やはり天気の良いのは良いですね。
展望を愉しんだら下りましょう。そのまま一関に下り、一気に自宅に向かいます。もう1泊して山に浸りたかったけど、腹八分にしておきます。
帰りも最短距離の常磐道で、福島に入ると周囲の賑やかな明かりが絶えてしまいます。
南相馬鹿島SAで浪江焼きそば食べて帰ってきました。
(美味しかった、SAが賑わっていてうれしかったです。)
(10/21) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
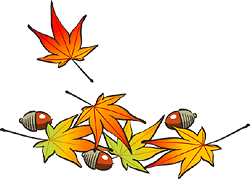 1ケ月も山登りから遠ざかってしまいました。 1ケ月も山登りから遠ざかってしまいました。
いろいろと野暮用が重なったり、天気のせいもあるのですが、弱気の虫がささやいたのが主因のような気がします。
そんな折、同級会のお知らせ、これをお出掛けの梃子に使ってと、宮城の山に出かけてきました。
狙いをつけたのは船形山、SAで仮眠しつつ、麓の登山口に朝着くような計画を組みました。
新しき相棒との長駆の楽しみもあります。
外環に入ってふと、ナビの指示を見ると東北道ではなく以外に常磐道経由をしめしています。
え!常磐道は2011震災の影響で通れないんじゃないの。時間に余裕があるので、試しにナビ通り行くことにしました。
そして通れました。いわき市の先からは対面交通、工事中でしたが仙台北部道路に通じ多賀城を経由して東北道に直結しておりました。道脇にはモニタリングポストが設置され、避難区域を突っ切っているんだという感覚が伝わってきて、やや緊張しました。
大和IC手前の鶴巣PAで仮眠、7時前に旗坂キャンプ場跡に到着、トイレを済ませ準備をします。
7℃前後か今朝は寒い。そしてガスガス状況、ちょっと残念、それでも昼の間は雨は避けられそうなので、7時、早々に出立します。
登山口に、赤く丸い30の白抜きの表示板を目にします。鼻から言ってしまいますと頂上が1で、29・28と順次ブナの樹に次々と高々と掲げられ(少なくとも10までは)登山者を頂上に誘い、見守ってくれているようです。
登山道は緩やかな傾斜が続き、ブナの森は緑から徐々に黄葉へと変化していき楽しませてくれます。
天気が優れないせいで森の中にはわたくし一人、豊かな気持ち浸りつつ、ゆったりと森を味わいながら歩を進めていきます。
言ってしまえば、それのみ山行でしたのです。が、それで良いのです、これを味わいに来たのですから。
三光の宮でも真っ白け、大滝キャンプ場からの路を合わせ、その先の分岐を蛇ヶ岳方向に進みます。
やや急こう配を登っていくと間もなく草原が現れて、ちっちゃな池塘らしき部分を通過します。
春の花咲くころ、展望の効く日などはさぞや魅力的な場所なのでしょう。
そして蛇ヶ岳(1400)に。森林限界を超え、すっかり葉を落としたツツジやナナカマド類の低木類が登山路を囲みます。
雨雫を宿したナナカマドの赤い実が印象的です。
更に歩を進めると観音寺コースとの出会い先が船形山山頂ということになる。
今日はガスの中、三角点と標識を確認するだけで、引き返すことにします。時に11時、風もあり寒い、吞気にランチをとる気分にはなれません。
帰りは升沢を下ることにしましょう。消えかけたマーキングや目印のテーピングを確認しながら、路を外さないように慎重に歩を進めます。
幾度か滑りつつ、もうそろそろかなと思う頃、沢を離れ升沢小屋が立ち現れる。覗いてみると明るく小ぎれいで、ここならゆっくり泊まれそう。
ここの庇を借りてランチとすることに。コンデンスミルク入りの甘~く、温かいコーヒーは何よりです。幸~せ。
後の帰り道は、今朝通った歩きやすいブナの路、もう一度味わいなおして、かえりましょう。
3時ごろ起点のキャンプ場に到着、今晩のお宿、台ヶ森温泉「山野川旅館」に向かったのでした。
(野生のタヌキ三兄弟が戯れている静かなお宿です)(10/19) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
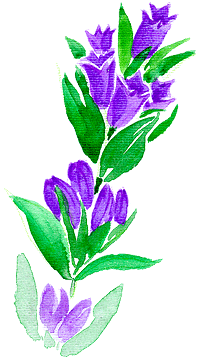 今年の夏は、お天気に翻弄された気がします。 今年の夏は、お天気に翻弄された気がします。
そして、ここにきて北海道の地震、この列島に住む限り、向き合わなければならない現実です。
頼りないけれど、その現実に直面している人々にエールを送り続けています。
さて、そんな言葉と裏腹に四国・石鎚山に出かけてきました。
高度恐怖症気味の私にとって石鎚山は難敵、そこで高いところ大好きの奈良の友を誘って挑戦することにしました。
奈良からスタートの感じ、まずは国民宿舎石鎚を目指します。
7時半頃出て渋滞の大阪市街を抜け山陽道に入り、瀬戸中央道で四国に渡り松山ICで高速を降り、大回りして石鎚スカイラインへ。
途中、若干の立ち寄りはあったものの、宿舎到着は16時頃でした。長かったですね。
さて、朝食をお弁当にしてもらって6時ちょっと前に出発です。
天気は曇り。予報では晴れ間があるという。ここの所秋雨前線の影響でスッキリしない天気が続いている。
これはラッキーというべきか。宿舎の横が登山口、迷うことがありません。
既に標高1500㍍付近、かなりズルした気分。先に泊まる場所を決めてしまったために、そうした結果になったのですけどね。
二の鎖小屋までほぼ1時間、いよいよ問題の鎖場、ところが通り過ぎてしまって、三の鎖だけの登りとなってしまいました。
途中、雲海に浮かぶ瓶ヶ森・伊予富士など周囲の山を目にすることができ、また意外に多い野草が道中を愉しませてくれ、昨晩からの不安を帳消しにしてくれました。
ともかく、待望の(?)鎖場、取り付きます。なかなか鎖の輪っかが登山靴とフィットしなくて、てこずったけど何とかクリア、石鎚神社に飛び出します。
ここが1,975㍍弥山頂上というわけです。その先に1982㍍天狗岳がそびえているはずなのですが見えません。
神社にお参りして、ガスの晴れまで待機、ガスが薄くなったところで天狗岳を往復します。わずかですが瀬戸内海も見えました。
その後、案じていたものも無くなり、スッキリした気分でランチ、宿のおにぎりを頬張ります。美味しい!
十二分に展望を満喫したら草花を愛でながらう回路をのんびり下ることにしましょう。もう秋ですね。紫色の花をつけた草花が多くなりました。
途中で修験者姿の親子孫三代のお参りの方とすれ違ったりして、今もなお信仰のお山であることを再認識させられました。
11時過ぎ、無事国民宿舎に帰着、ミッション終了とあいなりました。
後は愛媛の観光と美食を大いに楽しもうと、一気に石鎚スカイラインを駆け下ったのでした。(9/11.12) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| レイジンソウ |
イヨフウウロ |
リンドウ |
 |
 |
 |
| ハガクレツリフネソウ |
シコクブシ |
ミソガワソウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| サラシナショウマ |
アキノキリンソウ |
ナガバノコウヤボウキ |
シラヒゲソウ |
アキチョウジ |
タカクマヒキオコシ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ダイモンジソウ |
ヒヨドリバナ |
タカネオトギリ |
シロヨメナ |
ミカエリソウ |
トゲアザミ |
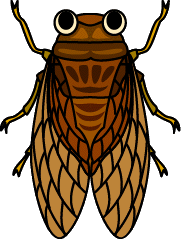 夏、真っ盛り過ぎる夏、やはり、ここは北アルプスでしょう。 夏、真っ盛り過ぎる夏、やはり、ここは北アルプスでしょう。
今回は古くからの友との二人連れ。友の提案で七倉山荘を起点に烏帽子岳を経て船窪小屋と繋ぐ周回コースを選択しました。
七倉山荘で合流、ここで一泊、明日に備えます。
良い温泉があり、夕食はジンギスカン、生ビールと山登りが萎えちゃいそう、ご用心あれ!
翌朝、5:20分発のタクシーで高瀬ダムに向かいます。ロックフィルダムの壮大さを目にしながらダム堰堤を登っていきます。
4人相乗りなので一人500円で済み、意外なお得感に心良くしての登山開始となりました。
吊り橋を渡り河原を横切って、いよいよブナ立尾根に取り付きます。
樹林帯をひたすら登るだけ、直射日光を浴びないだけ救いです。
三角点を過ぎると樹間から南沢岳の白く崩れた斜面が垣間見え、ゾクゾクします。
登山道脇の花も多くなり、足の進みの遅くなった私を癒してくれます。
そんなこんなで10時頃烏帽子小屋到着しました。小屋で宿泊手続きを終え、まずは寝床を確保します。第一関門突破です。
1時間弱休憩して空身で烏帽子岳を目指します。
烏帽子岳の分岐までは稜線漫歩、三ッ岳、水晶岳を背に赤牛岳を横に、針ノ木岳を前方に見据え歩いていきます。
足元にはコマクサ、イワツメクサ、タカネツメクサ、イワギキョウ、ミヤマコゴメグサ、ヤマハハコ…楽しいこと限りなしです。
前烏帽子岳を越すと眼前に屹立した烏帽子岳が立ち現れ感動的です。
岩をよじ登って標柱のある岩で証拠写真、岩のテラスで水休憩、展望を楽しみます。
後は小屋に戻ってゆっくりランチ、その後は昼寝タイム、優雅な時間です。
少し退屈になったら小屋外へ、小屋前はイワギキョウのお花畑、赤牛岳を真正面にしてのコーヒーブレイクは格別でした。
翌朝6時、船窪小屋に向けて出発です。今日は烏帽子岳には登らず南沢岳を目指します。
天気は快晴、というより暑すぎ、水の補給は欠かせません。ブナ立で2リットル以上消費、やはり同じくらい用意しての出発です。
南沢岳までは快適な稜線歩き、池塘もあり草花も豊富、その上極上の展望、何より静か、言うことありません。
ここから一気に下降、南沢乗越まで200メートル以上下ります。そして不動岳へ同じ程度登り返します。
不動岳から船窪岳間は今日のハイライト、ザレた斜面をロープを頼りに慎重に上下降を繰り返します。
船窪乗越まで辿り着いて、やっと到着のめどがたったしだい、結構ばてました。
キャンプ場奥に水場のマーク、荷物を降ろして行って見ることに。
が、なんとなんととんでもない所に水場がありました。崩れた斜面にそれはありました。水汲みも命がけです。
だからか美味しい水でした。この山域は水が手に入りにくい地域、水は本当に貴重なのです。
キャンプ場から船窪小屋までも意外に長い、15:30やっとこさ小屋に到着したのでした。
TV放映以来、一層人気の船窪小屋、槍ヶ岳の眺められるロケーションは抜群です。
食事は屋外のベンチでボルシチをいただきます。もちろんビールもいただきます。ちょっと寒いくらい、なんとも贅沢です。
バタンキューで寝てしまいました。夜中にトイレで起きて戸外に出ると星空が、とってもきれいでした。
最終日、我々は降りるだけ、最終組でゆっくり食事をいただいて、6時ちょっと前、小屋の人たちの鐘の音に見送られ、小屋を後にしました。
名残のチングルマを楽しんでいるとライチョウ親子と遭遇、思わぬサプライズに元気100倍です。
天狗の庭で高瀬ダムを見下ろし展望を楽しんだ後は一気に下りです。
9時半頃七倉山荘到着、ミッション終了となりました。
大町温泉郷で汗を流し、友と別れ、私はミッションⅡ、長岡に向かったのでした。(7/31∼8/5) |
 |
 |
 |
| 七倉山荘 |
七倉山荘のお風呂 |
高瀬ダム堰堤 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| タカネヤハズハハコ |
モミジカラマツ |
オヤマリンドウ |
ウサギギク |
ヨツバシオガマ |
タテヤマリンドウ |
 |
 |
 |
| 水晶岳に続く稜線 |
姿を見せた烏帽子岳 |
船窪に続く路 |
 |
| 烏帽子岳からの展望 |
 |
 |
 |
| コマクサ |
烏帽子小屋前のイワギキョウ |
ミヤマコゴメグサ |
 |
 |
 |
| 烏帽子小屋前でのコーヒーブレイク |
唐沢岳越しに見える浅間山・八ヶ岳 |
雲間に燕岳が |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| クルマユリ |
リンネソウ |
オオレイジンソウ |
ヤマハハコ |
エゾシオガマ |
ムカゴトラノオ |
 |
 |
 |
| 前烏帽子岳から船窪小屋への縦走路 |
南沢岳まえの湿原 |
富士山遠望 |
 |
| 南沢岳から 三ツ岳・水晶岳から立山 |
 |
| 南沢岳から 剱岳・立山から蓮華・針ノ木岳 |
 |
 |
 |
| クモイハタザオ |
タカネナデシコ |
シュロソウ |
 |
 |
 |
| シナノナデシコ |
トウヤクリンドウ |
イワギキョウ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| キヌガサソウ |
コイワカガミ |
アオノツガザクラ |
ミヤマキンポウゲ |
チングルマ |
イワツメクサ |
 |
 |
 |
| 槍ヶ岳遠望 |
船窪の水場 |
やっと、船窪小屋 |
 |
 |
 |
| 船窪小屋の夕食 |
ライチョウの親子 |
高瀬ダムを望む |
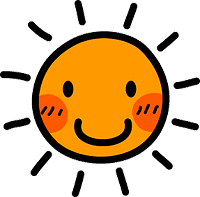 全く、この頃の天気はと常套句でも吐きたくなる猛暑です。 全く、この頃の天気はと常套句でも吐きたくなる猛暑です。
因果関係は皆無なのですが、屋久島に行った辺りから変な感じ…、被災地に小さなエールを送ります。
と言いつつ戸隠連峰、高妻山へ。
高気圧に覆われ天気が安定し、昼間の時間が長い今が、この季節に訪ねるのがベストと判断したわけです。
一泊するにはもったいない、一人じゃ、やはり車中泊の日帰りが妥当な線かな。
というわけで、冷えたビールの晩酌の誘惑を断って夕食後出かけました。
「道の駅しなの」で仮眠、夜明け前戸隠に移動、5時前駐車場を出発しました。。
朝の空気は心地よい。自宅を出かけるときに感じた'ねっとり感'と比べようのない格段のさわやかさ、行けそうな気がします。
牧場では牛が草を食んでいる。ちょうど朝日が昇るところ、今日も暑くなりそうではある。
間もなく一不動経由高妻山への登山口の表示、山道に入ります。沢沿いに路は作られている。遡行すると間もなく滝が現れる。
これが滑滝?右手に鎖が張られていて楽しく通過できる。
沢沿いには季節の草花が迎えてくれる。それを楽しみながら辿っていくと帯岩と呼ばれる一枚岩が現れ、横に鎖が張られ足場が切ってある。
岩の斜面にギボウシが咲いているのが目を引く。
最後に岩を這い上がると、難所を過ぎた感があり、氷清水で喉を潤し、あとは歩一歩と足を運んでゆくば避難小屋のある一不動の鞍部に到着です。
ここからは一不動から十阿弥陀まで道標のように辿って行けば良いので気は楽です。(多少の上り下りで足を使いますが)
尾根筋もお花が一杯、ついつい足が止まります。
九勢至を超えると高妻山の大きな山容が、ドカンと眼前に立ち現れます。山頂は弥陀の世界なのでしょう。
ここからが油断禁物、急登の連続、酷暑の夏は要注意、足がつりそうになりました。
ここでのペースダウンで10時頃の山頂到着、5時間程のアルバイトを強いられたことになりました。
雲も多めながら展望も利き、北アルプス北部の高き峰々を見ることができ幸せでした。
この日、頂上も暑かった。あまり長居もせず皆、早々に退散、私めもそれに習いゆっくり下山を開始したのでした。
帰りは弥勒尾根より下り2時過ぎ無事下山と相成りました。
牧場入口側のお蕎麦屋さんでお蕎麦を食べて、一路高速道をひた走って家路についたのでした。(7/19) |
 |
 |
 |
| 戸隠牧場 |
滑滝 |
帯岩 |
 |
 |
 |
| |
避難小屋 |
高妻山 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| タテヤマウツボグサ |
ハクサンオミナエシ |
シナノオトギリ |
 |
 |
 |
| ミヤマシャジン |
マルバダケブキ |
クルマユリ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ホタルブクロ |
トウギボウシ |
クワガタソウ |
|
サンカヨウの果実 |
モミジカラマツ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ズダヤクシュ |
シュロソウ |
アオヤギソウ |
ハナニガナ |
ヒメトラノオ |
ミヤマママコナ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
ヤマハハコ |
ノコギリソウ |
アキノキリンソウ |
シモツケソウ |
ノギラン |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ニッコウキスゲ |
ハクサンシャクナゲ |
ミヤマコゴメグサ |
ツルリンドウ |
ツマトリソウ |
オニアザミ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 長年、屋久島に行きたいなぁーと、思っていて一か八かの7月1日の格安航空券を購入、屋久島へ旅立ったと御覧じあれ。 長年、屋久島に行きたいなぁーと、思っていて一か八かの7月1日の格安航空券を購入、屋久島へ旅立ったと御覧じあれ。
一応、晴れ期待の旅立ちであったのですが、突如の台風発生!いやぁ、参った参った。
それでも、様子を伺いながら4日に宮之浦岳に登ってきました。
はじめは永田岳経由の縦走を考えていたのですが、一日だけの行程に、最短の淀川登山口からのピストンとなりました。
朝5時過ぎレンタカーで淀川登山口へ。入山料1000円を払ってトイレを済ませ、いざ出発です。
雨は、まだ辛うじて降っていない。歩き出しから屋久島感一杯である。つまり、全てが昏く蒼い。
ヤクスギだけでなく、モミ、ツガの巨木を多く目にする。巨木ヒメシャラの艶やかな木肌が特に印象的である。
そして、淀川小屋、淀川にかかる橋を渡る。その渓谷美が美しい。
ここから登りが急に、登り切って下ると小花之江河にでて一息、次いで花之江河に到着です。
晴れていれば此処で一服したいところ、が今日は先に進みましょう。
黒味岳もパス、今日は滑滝のようになっている花崗岩の岩肌を登って、展望が開けてくると、そこが投石平らしい。
ややガスがとれて岩峰が見え隠れする。見える山を宮之浦岳や永田岳と想像しながら歩を進めます。
ヤクシカやヤクザルが姿を見せます。
野草はヒメウマノアシガタ、ヤクシマカラマツ、ヒメツルアリドウシ、イッスンキンカ、コケスミレ、モウセンゴケ…と、出会えて嬉しい限りです。
でも、話によると今年はシャクナゲの当たり年、それは見事だったとか、是非とも再訪してその光景を目にしたいものです。
そして宮之浦岳山頂に、時間は9:45でした。台風の影響で前日、海も空も欠航とか、山頂は私ともう一人の単独行の二人のみ。
ちょうどガスが切れ、海は無理でも山並みを見渡すことができラッキー、山の神に感謝です。
またガスってきました。行動食のみで早々に下山します。まだ10時前後、ゆっくり楽しみながら下山することにしましょう。
花之枝江河まで来ると薄日ばさしてきました。頃も12:20、ここでランチとしましょう。
また雨雲がやってきそう。腰を上げます。
途中、屋久島らしい雨の歓迎をうけ、ぐっしょり、靴の中を濡らしながら、14:30淀川登山口に到着したのでした。(7/4) |
 |
 |
 |
| 淀川小屋 |
淀川橋 |
淀川 |
 |
 |
 |
| 花之江河 |
|
ヤクシカ |
 |
 |
 |
| 投石平 |
宮之浦岳から |
宮之浦岳から |
 |
| 宮之浦岳からのパノラマ |
 |
 |
 |
| 翁岳、安房岳、投石岳… |
 |
 |
 |
| ヒメウマノアシガタ |
コケスミレ |
ヤクシマミヤマスミレ |
 |
 |
 |
| モウセンゴケ |
ヒメツルアリドウシ |
イッスンキンカ |
 |
 |
 |
| ヤクシマカラマツ |
ヒメコナスビ(ヤクシマコナスビ) |
ヤクシマスミレ |
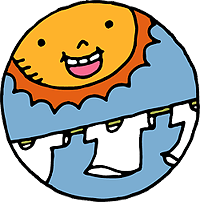 梅雨入り宣言直前、恵那山に行ってきました。 梅雨入り宣言直前、恵那山に行ってきました。
asiatoを辿ると2003年11月以来、15年ぶりとなります。記憶は飛んでいるので初めてと同じです。
今日はジム友と4人連れ、どんな感じになるかワクワク。
前日木曽路観光を果たし、6時過ぎ宿泊した月川温泉を立ち、広河原登山口へ、15分程で登山口到着です。
あれやこれやの登山準備で6:40頃、ゲートの横から林道を歩き出します。
20分程で本谷川を渡ります。前は橋が架かってなく渡渉したと、そうだったかなぁ。
そこから一気に高度を上げていきます。
陽射しに恵まれ新緑が美しい。
足元の花は期待薄と思っていたがユキザサが現れ喜ばせてくれる。
更に並んでミドリユキザサ(ヒロハユキザサ)も咲いている、嬉しくてテンションが上がります。
梅雨時と言えばZIO的にはマイズルソウ!群落でお出迎えです。
更に嬉しい上書きが、イチヨウランを発見!もう今日の山行はご満悦なのです。
8時半頃、尾根の急登終えると笹原が広がり青空にシラカバ・ダケカンバの新緑が映えて息を飲むほど美しい。
振り返る南アルプス連山が横一線に広がり、その前段に中央アルプスが木曽駒目指して立ち上がっていく。
今は梅雨時、雲が多く霞がち、前回よりクリアではないが、それでも見事な眺めである。
その地点からさらに一登り、9時半過ぎ、歩き始めて3時間、登りがやや緩やかになり、程なく山頂です。
10:15到着、コースタイム通りと言う事になりましょうか。
避難小屋でランチ、三角点2189.8より1.2㍍高い最高点2191地点をさがして少しウロウロ。
その後一気に下山、月川温泉で一風呂浴びて、飯田山本ICより中央高速へ、一気に帰千したのでした。(6/3.4) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ユキザサ |
ミドリユキザサ(ヒロハユキザサ) |
マイズルソウ |
 |
 |
 |
| ミツバオウレン |
ギンリョウソウ |
エンレイソウ |
 |
 |
 |
| カラマツ林 |
シラカバ・ダケカンバ林 |
避難小屋 |
 |
 |
 |
| イチヨウラン |
恵那山頂 |
ホソバテンナンショウ |
 |
 |
 |
 |
| ウラジロヨウラク |
コイワカガミ |
キケマン |
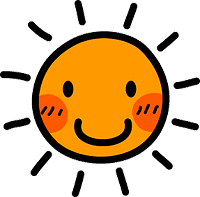 九州上陸四日目、やっと晴天が戻ってきました。 九州上陸四日目、やっと晴天が戻ってきました。
情報によると阿蘇の火山ガス規制が解除になるかも知れないと。
ただ、油断なりません。今朝のニュースでは霧島・硫黄山が小噴火レベル2に引き上げとか。
でも、この快晴、宿泊した休暇村南阿蘇からの阿蘇五岳の展望はおいでおいでをしているよう。
ともかく山頂駅付近まで行ってみることにしました。
9時頃到着、地方TV局のクルーが待機しているよう。
が話によると風向きが悪く火山性ガスの濃度が高く入山禁止規制が敷かれている模様。
風向きが変われば解除の可能性も有りと。
待つしかありません。地元の登山者と情報交換、午後になれば風向きは変わるからと云々。
ただ、問題が。今日は帰る日、帰りの飛行機が熊本空港15:50発、チケット購入済なのです。さあ、いつまで待てるでしょう。何処まで行けるのでしょう。
一回、二回とアナウンスがあり入山禁止です。三回目のアナウンス、規制が解除となりました。
時は10:15分、中岳までは行けるでしょうと踏んで出発です。ゲート前まで先ほどのTV局のスタッフに待ち受けられ一言二言、さて、どうなるのでしょう。
初め車道沿い、間もなく車道と別れて砂千里ヶ浜の縁を進んでいきます。
おぉ、やはり阿蘇の景観はすごい、火口壁の迫力は超弩級です。
やがて、一気に高度を上げていき稜線に出ます。
稜線は360度の展望、噴気孔の噴煙を左手に見ながら、正面に中岳・高岳を見据えて快調に歩きます。
12:15高岳山頂、皆さんはここで一服、登山者同士、情報交換に勤しんでおります。
ZIOめはゆっくりしている訳にはいきません。一息入れて下山開始、元来た路を戻ります。
砂千里への急降下は慎重に下りることにしましょう。
そして砂千里ヶ浜を横切って遊歩道に、そこから15分、13:45駐車場到着。
でも油断はなりません。熊本空港までの道がスムーズに走れるか疑問です。どのルートを選択するか悩ましい。
R325を選ばず、やや距離が延びるも県道熊本高森線を選択、結果正解、ストレスなく一気に行くことができました。
それでもまず給油所により満タンに、レンタカー会社により車を戻し、熊本空港に着いたのが15時過ぎ、搭乗手続き終えて15:10分。
15:20分までに搭乗口へとの指示に、何とか間に合ったのでした。
15:50分熊本空港を離陸。そんなこんなの旅も終えてみれば大成功!愉しい旅でありました。(4/26) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
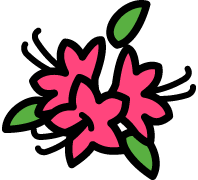 さて、高千穂に泊まって祖母山を目指す計画が雨で頓挫、さてどうしましょう。 さて、高千穂に泊まって祖母山を目指す計画が雨で頓挫、さてどうしましょう。
結果、西都原古墳群を訪ねたのですが、その顛末はマイブログにお任せして、翌日念願の祖母山を目指したのでした。
宿を早めに出発、五ヶ所から九州自然歩道になっている路を入る。長いなぁ~と感じる頃北谷登山口に突き当たる。
7時ちょい過ぎ、駐車場には先客が7、8台車を連ねている。
まぁ良い頃合いである。トイレを済ませ、登山届けを出して出発します。
天気は期待外れ、ガスっていますが雨でないので良しとしましょう。
北谷を渡渉して風穴コースに入ります。
うす暗い登山路、路脇にはマルバコンロンソウでしょうか、タチネコノメ・ワチガイソウも。スミレも多く見かけます。
風穴を過ぎると、いよいよアケボノツツジの出番です。
ガスの中、ピンク色の花がぼんやり見えています。それが遠く高木だったりしてなかなか良い画が撮れません。
これも素人のご愛嬌、許していただきましょう。
そして花を愛でながら高度を上げていくと間もなく祖母山山頂、この辺りはまだ蕾、やはり見ごろはGWでしょうか。
展望も残念ながら利きませんでした。祠にご挨拶をして暫し休憩します。
でも花も展望もなければ長居は無用、国観峠方向へ周回コースで下山します。
障子岳へのルートも考えたのですが、気持ちが戦闘モードになっていません、パスしてしまいました。(;´д`)トホホ。(4/25) |
 |
 |
 |
| 北谷登山口 |
|
風穴 |
 |
 |
 |
| ピークが見えてきました |
祖母山山頂 |
大分・熊本・宮崎三県境界 |
 |
 |
 |
| マルバコンロンソウ |
タチネコノメ |
ワチガイソウ |
 |
 |
 |
| ?スミレ |
ミツバツツジ |
アケボノツツジ |
 |
 |
 |
| アケボノツツジ三様 |
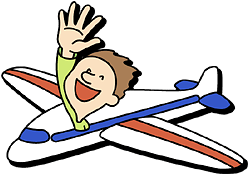 ナ、ナント単独飛行機で九州まで出かけてきました。 ナ、ナント単独飛行機で九州まで出かけてきました。
驚く事態が、ナ、ナントなのですが、明かせば一人で飛行機に乗ったことがなかったのです(冷汗)。
ZIOめにとっては云十歳にして大冒険なのでありました。
これがクリア出来れば、目指す祖母山は半分成功したようなものという認識でした。
話を戻しましょう。アケボノツツジに憧れて祖母山行きを計画しました。
成田から熊本へはジェットスターで、そこでレンタカーで行動、あとは問題は天気でした。
ところが晴天の続きは出発日(23日)まで、強力な低気圧が近づいているとのこと、何とも間の悪いZIOめであります。
そして、明日は確実に雨、そこで、9:35分熊本空港に到着したら、そのまま阿蘇山に遊びに行くことにしました。
ただ、事前の情報通り中岳への登山ルートはガスのため閉ざされていました。
とりあえず登れる山に登ることに、まず烏帽子岳から行きましょう。
草千里を眺めながら、若干場違いの感もありつつの登山開始です。
足元にはハルリンドウがあちこちに、野焼きの後にいち早く顔を見せたんですね。
ミツバツチグリも居ました。黄色といえばキスミレもいっぱい、嬉しいかぎりです。
ミヤマキリシマは開花寸前というところでしょうか。
烏帽子岳山頂は数メートル手前をロープで囲っていました。ちょっと覗いてみましたけどね。
展望があまり利かないものの眺望を愉しんだら下山しましょう。次に杵島岳に行くことにしましょう。
頂上まで石段が続く面白味の少ない山でしたが、杵島山山頂から続くお鉢巡りは愉しめました。
取り敢えず2座登ったということで、今日は此処までにして高千穂の宿に向かったのでした。(4/23) |
 |
 |
 |
| 草千里からの烏帽子岳 |
烏帽子岳山頂 |
烏帽子岳山頂からの展望 |
 |
 |
 |
| 杵島岳火口壁 |
杵島岳山頂 |
杵島岳からの米塚 |
 |
 |
 |
| ハルリンドウ |
ミツバツチグリ |
キスミレ |
 |
 |
 |
| ノジスミレ |
フモトスミレ |
ミヤマキリシマ |
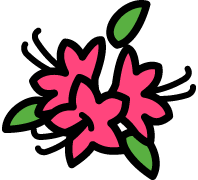 少しご無沙汰していた丹沢、、小田原からのお呼のついでに、ちょっくら立ち寄ることにしました。 少しご無沙汰していた丹沢、、小田原からのお呼のついでに、ちょっくら立ち寄ることにしました。
目標は檜洞丸、シロヤシオの開花には少し早いかも知れないけれど春です、何方かと出会えるはずです。
西丹沢自然教室に7時前に到着、今日は晴れるはずだったのだが、雲が多くどんより気味、まぁ、それも良し。
トイレを済まし届を出して早速歩き出す。大室山を正面に見て心が高揚する。路脇にはヤマブキの黄色が鮮やか、気持ちが良い。
間もなくツツジ新道登山口に。ゴーラ沢出会いまでは新緑を愉しみながら、足元にはキランソウやタチツボスミレがいっぱい、嬉しい限りである。
向かいの斜面には山桜が彩りを添えて華やか、トウゴクミツバツツジも見頃、その艶やかさにしばしば足を止めてしまう。
そしていよいよツツジ新道、一気に高度を上げる。
石棚山稜の分岐の木道に辿り着く。辺りの木々はまだ芽吹き前、ガスってきて少し荒涼としている。
バイケイソウも芽吹いたばかりのようだ。
10:10分檜洞丸山頂、ランチに早いけど軽く済ませましょう。
ランチ後、何かないかと一巡り、居ましたキクザキイチゲが、三輪ほど咲いておりました。
15分ほど休憩して下山開始、今日は石棚山稜を下ることにしましょう。
この路は丹沢らしい崩落があっちこっち目にする路、でも素敵なブナ林に出会える路でもあった。
以前、西丹沢県民の森から入山した時に通過したはずなのだが、これほどの林だとは感じていなかった。
そして、足元にハナネコノメが、今年は出会えないとあきらめていたのに、こんな山の上で見ることができるなんて感激である。
ヤマネコノメも並んで咲いている。スミレもいっぱい、葉脈が赤いのでアカフタチツボスミレか、距の白いタチツボスミレはどなた?
ヤブ沢ノ頭辺りでエイザンスミレとご対面、そこから箒沢までは、中々難所でしたが、愉しいコースでもありました。
板小屋沢辺りではマルバスミレにも出会えてうれしい限り、これでは中々先へは進めません。
西丹沢自然教室に辿り着いたのが14時頃、7時間の周回コース、結果的にかなり満足の花探しの山行でありました。(4/16) |
 |
 |
 |
| ヤマブキの花に見送られて、いざ出発 |
ヤマザクラの彩り |
トウゴクミツバツツジも姸を競う |
 |
 |
 |
| 芽吹いたばかりのコバイケイソウ |
檜洞丸山頂 |
石棚山稜の崩壊地 |
 |
 |
 |
| ミヤマシキミ |
板小屋沢 |
キクザキイチゲ |
 |
 |
 |
| タチツボスミレ、距がしろいけど? |
? |
アカフタチツボスミレ |
 |
 |
 |
| エイザンスミレ |
? |
マルバスミレ |
 |
 |
 |
| ヤマネコノメ |
ハナネコノメ |
ミツバコンロンソウ |
 |
 |
 |
| ミツバツチグリ |
キランソウ |
ミヤマキケマン |
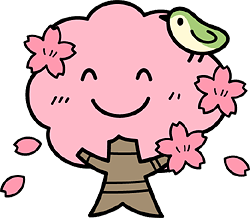 関東は桜の季節があっという間に過ぎ去ってしまいました。 関東は桜の季節があっという間に過ぎ去ってしまいました。
うっかり!近場には行きそびれてしまいました。
そこで考えました。こちらから会いに行きましょう。
何処へ、咲いてる所に。
安曇野の光城山が咲いているという。明日は晴天、思い立ったが吉日、と出かけてきました。
ヤマレコを参考にしたのですが、さて。
安曇野ICを出て、田沢駅へ。そこから線路沿いに走りながら光城山登山口を探します。
直ぐに見つかりました。今日10日から桜まつり、スムーズに登山口駐車場へ到着です。
登り口の桜は既に満開、情報は正確でした。
9時ちょっと前、もう、ルンルン気分で歩き出します。振り返ると、おぉ、常念が白く輝いて立ち上がっているではありませんか。
勿論、常念だけではなく、蝶ヶ岳から後立山連峰の白馬まで一直線、白き峰々が連なっている。
そして紺碧の空、もう言う事がありません。目的は達成したようなもの。あとはユルユルと花見を愉しみましょう。
本当に緩々とファインダーで桜と山を覗きながら登っていきます。
三角点のある光城山は、北アルプスの絶好の展望地、三々五々登ってくる人々がお弁当を広げている。
10:15過ぎ、早いけど何かおなかに入れていきましょう。
足元にはセンボンヤリが、白い花と紫色の蕾がありました。
さて、十分休んだら長峰山に向かいましょう。ほぼ、道路を横移動、程なく展望台のある長峰山につきました。
人工構造物はあまり好きじゃないけど、登ってみると正に360度の展望台、素晴らしい展望でした。
ここでもノンビリして、尾根を降ります。安曇野の街と白く輝く山並みを見ながらの下山、愉しいですね。
長峰荘まで下りれば、生活道路を起点まで歩きます。
でも、ここは安曇野、双体道祖神があったり、光の五社の社殿あったりと退屈しません。
畑仕事のご婦人と一言二言会話したり、14時過ぎ駐車場辿り着きました。5時間強のユルユル・ハイクでありました。(4/10) |
 |
 |
 |
| 兎に角、常念岳がセンターを張っていました |
  |
 |
 |
 |
| 光城址 |
古峰神社 |
光城山頂上広場 |
 |
 |
 |
| センボンヤリ (白) |
ミツバツチグリ |
ダンコウバイ |
 |
 |
 |
| センボンヤリ(紫) |
ハクサンハタザオ |
山桜 |
 |
 |
 |
| チョウジザクラ |
ウグイスカズラ |
ヤマブキ |
 |
 |
 |
| 民家の花桃と北アルプス |
道祖神 |
光城山 |
 雪の浅草岳を下りれば、下界は春爛漫、里山は山桜が点々と山を彩り始めています。 雪の浅草岳を下りれば、下界は春爛漫、里山は山桜が点々と山を彩り始めています。
そして関東は、桜吹雪の頃。桜といえばイワウチワの咲くころでもあります。
気になっている場所があります。茨城県北・横根山のイワウチワです。
昨年2017年は4/15に鉄五郎新道で、2015年は日立・御岩山でイワウチワに出会えましたが、今回はどんな感じでしょう。
花貫渓谷と花園渓谷を勘違いして一時間ほどタイムロスしましたが、9時過ぎ花貫ダムサイト、桜公園駐車場に到着することができました。
近年事故があり、ご推奨コースではない模様。それでも、それなりにハイカーが入っているようだ。
9時過ぎ、出発です。およその検討をつけピンクテープに従い山道に入っていく。
それなりの急斜面、いかにもイワウチワの好きそうなロケーションである。
間もなく白い花の一群に出会う。これこそイワウチワ、ドンピシャで咲いていました。
後はファインダーをのぞきながら欣喜雀躍、這いつくばりながら登っていきます。(もっとも、自宅で確認した画は情けないものばかりだったのですが)
高低差150㍍くらいはあるでしょうか、その間の登山道脇に群生開花しておりました。
登り切ってしまえば、そこは里山、特にないのですが三角点のある横根山を訪ねて見ましょう。
先客があり、ランチしていたので早々に退散、さて、どうするか?道が続いている都室山まで足を延ばしてみましょうか。
分岐地点で沢尻湿原の表示が、覗いてみましょう。
乾燥化が進んでいて、わずかに水芭蕉が咲いているのみ、少し残念な湿原でありました。
分岐に戻り都室山へ、表示板には2.5㌖と記してある。辿ってみましょう。路はしっかりしていて迷うことは無さそうです。
花貫ダム湖の南側を尾根伝に辿るコースです。里山の雑木林を愉しみながら歩く感じ、早春とか晩秋が似合うコースかもしれません。
途中でランチ、都室山は休憩に都合の良い三角点(449m)のある平坦な場所でした。スミレ見~つけた。マキノかシハイかヒナか、悩ましい。
1:15分、後は下るだけ、30分ほどでR461に出ます。あとはテクテク、ダムを周回、起点まで3㌔m程か、ダムを見学しながら2時過ぎに到着。
5時間ほどの、愉しいハイキングでありました。
帰りに、高萩市の中郷とうりゃんせ温泉で汗を流して帰路についたのでした。(4/3) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| イワウチワ六態 |
 |
 |
 |
| ヒナスミレ三態 |
 |
 |
 |
| アセビ |
ミズバショウ |
都室山 |
 |
 |
 |
| ヤマネコノメ |
キブシ |
花貫ダム・さくら公園 |
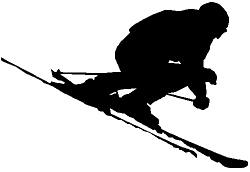 今年も雪踏みをしようと、浅草岳に出かけてきました。 今年も雪踏みをしようと、浅草岳に出かけてきました。
昨年と同じ計画で南魚沼の大雲沢ヒュッテを起点に計画したのでしたが、いろいろありまして一人だけになってしまいました。
しゃ~ない、一人で気ままに行くことにしました。
途中、西上州の神成山を足慣らし選び、2時間ほど歩いてから宿へ、翌日宿のオーナーと浅草岳を目指しました。
朝6時過ぎ、除雪されている大自然館前で車を置き出発です。
白崩沢に沿って遡上、ムジナ沢とヤヂマナ沢の間の尾根に取り付いて高度を上げていきます。
左手の対岸に滝が見えます。大きな滝です。この時期にしか見られない滝の様です。
さらに高度を上げ900㍍近くなると後ろに守門岳の雄姿がしっかりと確認できるようになりました。
そして、行く手の一つの目標、嘉平与ボッチの三角錐の頭が確認できるようになります。
見晴らしが良くなり、尾根を雪庇、割れ目に注意しながら進んでいきます。
嘉平与ボッチ辺りは亀裂があり、巻かずにピークを超えて通過します。
前岳までたどり着けば一安心、浅草岳まではもうすぐ、展望を大いに楽しみながら進みます。
北に粟ヶ岳、北東に御神楽岳、北東に守門岳、南に会津朝日岳、その奥に燧ケ岳、荒沢岳、越後駒、八海山も確認できる。
何ともすごいパノラマである。
5時間かかって浅草岳到着。風が強い。証拠写真だけ取って、早々に下山、なだらかな雪原を県界尾根を粟が岳を正面に見ながら下っていく。
山スキーをやる人には堪えられない豪華な雪原が広がっている。
一時間ほど下った雪原でランチ。
雪原のきれたあたりから林道に向かって急降下、林道に降り立ってからも1時間ちょっとアルバイト、3時過ぎ起点に到着したのでした。
9時間の雪中行軍、疲れました。でも、充実の一日でありました。(3/29) |
 |
 |
 |
| 出発 |
白崩滝 |
守門岳の雄姿 |
 |
 |
 |
| |
嘉平与ボッチ目指して |
|
 |
 |
 |
| 嘉平与ボッチを乗越して |
鬼ヶ面山の爆裂火口 |
浅草岳、もう一息 |
 |
 |
 |
| 浅草岳山頂 |
田子倉湖を望む |
正面に粟が岳を見て雪原を下る |
 |
 |
 |
| 振り返ると… |
守門岳 |
浅草岳 |
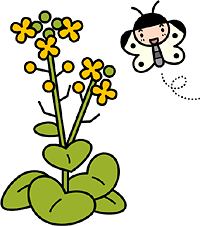 春が猛ダッシュでやって来たような今日この頃、ではその証拠でも探しに行こうかな。 春が猛ダッシュでやって来たような今日この頃、ではその証拠でも探しに行こうかな。
さて何処へ?青梅線と五日市線の間に広がる丘陵地帯が気になっていた。そこを訪ねて見ることにしましよう。
起点は先日、羽村堰を訪ねた時に目星をつけておいた日の出村・野鳥の森、入口の一つ、谷の入り口。
谷ノ入会館の先にこじんまりした駐車場が整備されていて、ちょっとした施設もできるらしい。
「野鳥の森」も今は仮称、おいおい整備していくつもりらしい。そのままにして欲しい気がしますけど、さて・・・。
兎も角、出発しましょう。
まずは尾根道に出て、先日ちょこっとだけ歩いた西多摩霊園方向に歩いていきます。
カンスゲの花が迎えてくれます。良かった。
まもなく見覚えのある尾根道に、大岳山の展望が得られる気持ちの良い路です。
アセビの花が感じ良い。
菅生方向に歩いてみますが、舗装道路に出るのは如何にも面白くない、二ッ塚峠と反対方向、分岐まで引き返すことにします。
野鳥の森と花火工場の間を通り抜け、東海大菅生高校の横をいきます。若人の声は時に野鳥のように心地よい。楽しい道です。
そして分岐、二ッ塚峠まで足を延ばしてみましょう。この路は古道然としていて、マウンテンバイクが入ってきたりするようです。
4等三角点二ッ塚を見つけました。そこを引き返し点とすることにしましょう。
足下田に下る古道を選びます。が、今はあまり使われていなそうで、倒木が道を塞いでます。
足下田川沿いに下り、熊野神社、東光寺を経て東光院から、再び野鳥の森へ。
猿取山から妙見宮方向へ、途中から谷ノ入古道に下り、起点に戻ったのでした。
とりたててアップする程の画はなかったのですが、いや、タチツボスミレに出会えました、気持ちの良い歩きとなりました。(3/13) |
 |
 |
 |
| 谷ノ入り口 |
|
尾根道 |
 |
 |
 |
| 奥多摩三山を望む |
馬酔木 |
西多摩霊園 |
 |
 |
 |
| |
二ッ塚4等三角点 |
|
 |
 |
 |
| |
熊野神社 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| マンリョウ |
タチツボスミレ |
カンスゲ |
オオイヌノフグリ |
ヒメオドリコソウ |
ハコベ |
 払沢の滝は、あの後完全氷結したのだとか、めでたしめでたしであります。 払沢の滝は、あの後完全氷結したのだとか、めでたしめでたしであります。
久しぶりに、高村光太郎ばりのキッパリとした冬がやって来たわけですね。
そんな冬をやり過ごしてしまうわけにはいきません。
腰を上げて雲取山でも行ってみましょうか。
なかなか、新雪だぁーそれゆけぇとはいかないのが、地理的辛さ。何せ高速も外環も止まって動きようありませんから。
今日は好天、それに雲取なら踏み後も一杯、安全に雪の感触を愉しめるでしょう。
7時半ちょっと前、丹波山村営駐車場に到着。案の定、小袖の駐車場はもう10台以上の車が、盛況盛況!
おや、トイレ棟が建っているのですね!でも閉鎖している、残念。
路面には雪が無く、取り敢えずアイゼンは未装着で出発します。
登山口には大きな表示板、これにもビックリ!丹波山村作成。そして将門伝説をとりこんだゲーム感覚の迷走ルートの表示板。
ちょっとの間にドンドン変わっていくですね。1から10まで、全部訪ねたい気分にさせられます。
それはともかく登山道に入ると、すぐ雪が現れましたが、そのまま進んでいきます。
皆さん早い、さすが日帰りピストンを念頭の登山者、健脚自慢が集まっているようです。
頑張りましょう、ひたすらテクテク。堂所までくれば何とか目鼻、富士山の遠望は如何に?今日は叶わなそう。
ブナ坂への分岐辺りでアイゼンを装着、ここからは雪の感触を愉しみながら一歩一歩歩くことにしましょう。
石尾根に飛び出せば快適な尾根歩きが待ってます。
石尾根は快適である。今日は富士は見えねど陽射しがあり、雪と紺碧の空が素晴らしい。
奥多摩小屋を過ぎ山頂ももう真近、若者がテントを設営している。もう真似できないなぁ。
雲取山山頂には4、5人の先着さん、共に展望を愉しみました。
避難小屋でランチして、後は一気に下山したのでした。
3時半過ぎ駐車場到着。今日も良き山行でありました。(2/4) |
 |
 |
 |
| 丹波山村村営駐車場 |
小袖コース登山口 |
わずかに富士山が |
 |
 |
 |
| ブナ坂 |
石尾根 |
 |
 |
 |
| 積雪は30㎝位か |
避難小屋が見えます |
雲取山頂上から南アの稜線 |
 |
 |
 |
| やはり人気の山です |
奥多摩の山々 |
雪と青空、似合います |
 皆さま、あけましておめでとうございます。 皆さま、あけましておめでとうございます。
2018年が始まりました。
それにしては、遅い始まりです。もう、半月も過ぎました。
なにか、アイドリングに時間がかかって、やっと始動したZIOめでございます。
そんな怠け者を見捨てず、今年もご贔屓にして頂ければ、何よりでございます。
いくばくかのいいね!でキャンキャン喜んで励みますので、今年もよろしくお願いいたします。
で、結構寒い日が続く今年、払沢の滝の凍結具合を見ながら、浅間尾根を歩いてみようかなと思い立ち出かけたのでした。
8時頃駐車場に到着、早速滝を覗いてみることにします。
夜明けとともに撮影に訪れているようで、幾人もの三脚付のカメラを抱えた方とすれ違います。
一昨年来た時より氷結している気はするのだが、はて、氷結度合何パーセントなのか?
兎も角、見ることができ満足、さて時坂峠に向かいましょう。
民家の間を通っていくこの道が私は好きです。特に桜の季節は!今年も機会を作って来ようかなぁ。
林道を歩いていると目につくのが植林の伐採痕、この辺りはどんどん風景が変わっていく。
林道が尽きれば登山路へ。少々暗い路を我慢すれば間も無く、雑木が美しい浅間嶺、その前に松生山に寄って行こうかな。
以前訪れたときは何も展望のない面白味のない山と認識していたのだが、な何と、中継所になっているのですね。
そして南西面が切り開かれ絶好の富士山の展望地に衣替えしていたのです。
頃は11時過ぎ、ここをランチ場所と決めました。
今日は風もなく小春日和、そして何よりのご馳走、秀麗な富士山が眼前に。
方針転換!ここでまったりして、笹平BSに下ることにしましょう。
笹平までは予想よりちょっと長かったけど、それもまた良し。
檜原街道を払沢の滝Pまで、4キロ㍍強、ここが一番長かったかな、15時前に到着、ミッション終了。
結果的に愉しい山行となりました。(1/16) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 浅間林道から |
 |
 |
 |
| |
浅間嶺分岐 |
松生山 |
 |
 |
 |
 |
| ご存知富士山 |
御前山 |
大岳山 |
 |
 |
 |
| 笹平への尾根道 |
払沢の頭 |
笹平BS |
| |
|
 |
|
|

