![]()


![]()
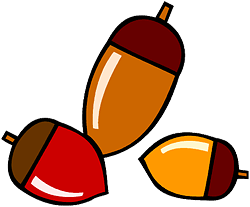 12月は千葉の山の月、と勝手に考えているZIOめ、さて何処に出かけましょう。 12月は千葉の山の月、と勝手に考えているZIOめ、さて何処に出かけましょう。軽く、静かに愉しめるところはと決めたのが房州アルプス。山の無い千葉県にアルプスと言う何とも強引なネーミング。 兎も角、訪ねてみることにしました。 工程の難所、年中渋滞の千葉ICを通り過ぎれば後は楽ちん、市原Pでトイレを済ませ、食料・飲み物を調達して、いざ出発です。 富津中央ICからR465東進、押切で県道に入り志駒川沿いに南下、志駒不動の水に立ち寄って林道鹿原線入口を確認。 登山口入口についたのが9時過ぎでした。道路側スペースに車を止め9時半ちょっと前、林道鹿原(しっぱら)線を辿っていきます。 高度が上がると右手に展望が開け郷の景観が目に入ってきます。心地よい風景です。 更に進むと富士山が見えてきました。手前の工場群は京葉コンビナート、東京湾越しに見えているのでしょう。 何故か嬉しいです。これを見に来たような気もします。肩の荷が下りたよう、あとは気ままに歩を進めることにしましょう。 まもなく林道とお別れして房州アルプスの表示板に導かれて山道へ。なだらかな道が続きます。 時折、西側の展望が開け東京湾と富士山が同時に望め、テンションが上がります。 山道は房総半島特有の照葉樹林帯、木漏れ日が差し、中に紅葉した落葉樹が混じっていたりして、良い加減です。 愛宕神社に立ち寄っていきましょう。秋祭りの後か幣が新しく今も里人の奉斎を受けている感じがあって新鮮でした。 もとの路に戻り進みます。岩が露出している付近は展望が開け愉しいところです。 そこを過ぎるとまた樹林帯へはいり、そして今回の唯一のピーク267㍍二等三角点へです(無実山の表示板がありました)。 ここからは照葉樹林の中を下っていきます。やがて路はマテバシイの純林の中を抜けて行きます。めったに見ない景観、思わぬサプライズです。 やはり歩いてみなければわかりませんね。間もなくミカン畑が現れ民家が近いことを知らせてくれます。 番犬に吠えられながら民家の脇を通り抜けると舗装道路に飛び出ます。 陽射しが気持ち良い。道路の斜面にはスイセンが一杯、もう大分咲いています。 頃は12時半、ここで道路脇にシートを広げランチタイムとする事にしました。 やぁおにぎりが美味しかった。 後は舗装道路を下るだけ、30分程で県道に出ます。県道沿いの「山中温泉陽気の湯」目指したのですが残念!しまっていました。 電話で問い合わせると修理中、年内は開けないとか、皆様もご用心。 後はひたすらモミジロードを歩いて出発点鹿原林道入口まで戻ったのでした。 目的通りらくちんで静かで愉しい山行でありました。(12/9) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 林道鹿原線入口 | 中郷集落 | 富士遠望 手前に煙突、右奥に南アルプス | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 房州アルプス入口 | 富士山と東京湾 | 愛宕神社への路 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 愛宕神社 | 267㍍ピーク(無実山) | マテバシイ純林の路 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 照葉樹林帯に彩りを | マテバシイ繁る路 | マテバシイ純林 | |||||||||
  |
 |
 |
|||||||||
| スイセン二題 | 房州アルプス内台入口 | カントウヨメナ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| トネアザミ | 志駒川もみじロード | ||||||||||
 ぼやぼやしているうちに、紅葉シーズンが関東の山々を通り抜け、ZIOめは大慌て。 ぼやぼやしているうちに、紅葉シーズンが関東の山々を通り抜け、ZIOめは大慌て。その名残りでも探しに出かけようかと奥多摩に車を走らせました。 目指すは日原・八丁橋、今日の予定は唐松谷から石尾根縦走路に出て雲取山へ、奥多摩小屋に泊まって野陣尾根を下り日原に周回するコースです。 今回もジム仲間との4人旅、ノンビリモードで山行を愉しむのが趣旨というわけです。 予定通り9時半前に八丁橋ゲート前に到着、9時20分頃歩き出します。 日原林道沿いの紅葉模様もほぼ終盤、少し遅すぎました。 でも良いんです。初冬の風景も乙なものです。 コースタイム通り10時40分頃林道を離れて登山道へ。吊り橋をわたって山に分け入ります。 そして唐松谷と野陣尾根の分岐点へ。 最近まで唐松谷へのルートは通行止め、Hgさんの情報を信じやってきたのですが大丈夫そうで一安心、先へ進みます。 油断は禁物、慎重に歩を進めていきます。まもなく木の橋が現れますが整備されていて安心して通れます。登山道の整備ありがとうございます。 やはりモミジ見物できないのはちょいと悔しい、来年にかけましょう。 谷を見下ろすと動く黒っぽいものが!熊かと思いきやカモシカの親子連れよう、始め大小2個体、後からもう1っ匹カモシカが、彼らの領域にお邪魔します。 最後の新しくできた木橋をわたりたおやかな山襞を辿っていきます。途中でランチして、やがて最後の沢を渡り石尾根への登りの開始です。 14時15分頃石尾根到着、おぉ~、富士山のお出迎え嬉しい限りです。申し遅れました、本日は天気は無風快晴、終日素晴らしいお天気だったのです。! だからもうルンルン気分で奥多摩小屋へ。早速宿泊手続きをし、荷物をデポして雲取山山頂を目指します。 15時半過ぎ到着しました。以前あった雲取山表示板から2017年表示ポールが立っていたのですね。そう、今年はじめての雲取です。 展望を堪能するも、もう夕暮れ時、夕飯の支度をしなければ、日没と競争です。 日没と富士の景観を愉しみつつ水を汲みコンロを設定ing、陽が沈むと寒いこと寒いこと、小屋の中でできたのですがそれでも寒い、ストーブのリクエストをしてしまいました。それでも寒い。外に出てみると月と富士山とのコラボレーション、下手な撮りてでも思わずカメラを向けたくなる構図でありました。 消灯時間ぎりぎりまでストーブ周りで粘って就寝に。思い切りすべてを着込んで小屋の寝具も利用しつつシュラフに潜り込みます。 小屋番さん、凍るから飲料水もガスボンベも布団の中に入れておいたほうが良いよと。 翌朝、下山だけなので、ぎりぎりまでシュラフの中、日の出とともに起きだした感じ。富士山は頭だけを雲の上に突き出しておりました。 8時20分小屋出発、野陣尾根を下ります。 カラマツはすっかり葉を落とし冬木立に、サワラノ平辺りでは北方向に白い山が、方向からすると浅間山だろうか、立山連峰は見えるのだろうか? ご存知の方は教えてください。 キツツキ(コゲラかな)が木をつついていました。 そして一気に下ります。10時40分頃唐松谷との分岐に、12時20分頃起点八丁橋に戻ってきました。 「もえぎの湯」で汗を流して帰路についたのでした。(11/21.22) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
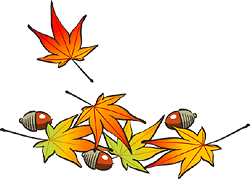 また、今年の天気は・・・で始と。まりそうです。 また、今年の天気は・・・で始と。まりそうです。シーズンオフ真近の平ヶ岳登山、今日しかないと、突然決行!ジムのお仲間と行ってきました。 13日(金)13:30出発、関越小出ICよりR352で鷹ノ巣清四郎小屋まで一目散、何とか6時ちょっと過ぎに辿り着きました。 ルートはちょこっとだけお手軽ルート、登り口を中ノ岐林道詰める、世に有名なプリンス・コースを選択。 翌朝、小屋の車で登山口へ、5:40頃出発です。登り始めは薄暗い中、ひたすら高度を稼ぎます。 予報を晴れも期待できると踏んだのですが、ままならずガス模様に終始、雨にならないだけ良しと思い直しての登山でした。 8時頃2000㍍越え湿原に飛び出す。 紺碧の空に只見の山並み、草紅葉の対比を妄想していたのですが残念!ガスの中の湿原風景となってしまいました。 まぁ、それも良し。玉子石を見て平ヶ岳を踏んで、もう帰り支度。 展望ゼロの肌寒いガスの中、のんびり、休憩モードには、とても浸れなかったというのが実情でした。 それでも、姫ノ池のある池ノ岳までの道筋はさすが平ヶ岳、2000㍍頂上でこんな景観があるなんてと、感激でした。 実は40年程前、登ってはいるのだが、ほとんど記憶が無く、今回しっかりと足跡を残すことができ、連れに感謝です。 雰囲気を満喫したら、鷹ノ巣目指して下山開始、滑りやすい木道に苦戦しながらも紅葉黄葉の彩りに目を移しながらの山歩きは愉しさいっぱいです。 台倉清水でランチ、コンロを使って熱々ラーメンをすすります。ここで思い出しました、40年前ここでビバークしたことを(時効ですよねー)。 台倉山を登りきるとご褒美が待ってました。紅葉です。奥只見の山々が紅葉に彩られているのが目に飛び込んできたのです。 ガスが切れ、その素晴らしさを垣間見せてくれたのです。燧岳も僅かに姿を現し、望外の喜びに欣喜雀躍といった感じでした。 それからは、痩せ尾根もルンルン気分、3時過ぎに清四郎小屋に到着、お風呂を使わしてもらって一服、一路松戸を目指したのでした。(10/14) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
  |
 |
|||||||||
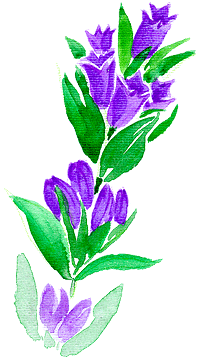 今年の天気は本当に不安定、光岳への登山計画が幾度か中止となりました。 今年の天気は本当に不安定、光岳への登山計画が幾度か中止となりました。光小屋の営業終了が迫る中、今シーズン最後のチャンスとして10日出かけてきました。 登山前日、遠山郷に泊、翌朝4:30遠山タクシーで易老渡に向かいます。 5:30易老渡着、いよいよスタートです。 880㍍の登山口から2354㍍易老岳までの一気の登りは、荷物が少々重いだけに、中々手強い。 面平まではひぃひぃ、そこからは一歩一歩、植林帯、皮肉にも花が少ないので歩くのには専念できます。 それでもセリバシオガマをよく見かけました。 易老岳からの横移動はトリカブトの花が盛り、大いに愉しませてくれました。 三吉平と静高平の間には枯れた沢、ゴ~ロの嫌らしい路が待ってました。 が、超えればセンジヶ原、亀甲状土の面白い景観が迎えてくれます。 イザルヶ岳立ち寄るも真っ白け、天候が下り坂、残念です。 13:40光小屋到着、先ず手続きを済ませてから光岳へ。そして光石まで足を伸ばします。 そして、ナ、ナント、ミヤマムラサキの花が一輪、待っていてくれたのです。何とも嬉しいご褒美でした。 雨が降り出しました。小屋に戻って夕食の支度をしましょう。 翌朝、風雨が収まりません。予定では聖平小屋までですが、さて、どこまで進めることができるやら。 易老岳までは来た路を戻ります。時折降りが激しく、登山路は雨水路に。 易老岳から茶臼岳へ。登山路は水溜り、ほとんどずぶ濡れ。茶臼岳が近付くと風もさらに強くなって、吹き飛ばれそう。 早々に茶臼岳を下ります。茶臼岳小屋分岐で決断、今日の上河内岳経由の聖平小屋は中止することにしました。 途中下車の茶臼小屋、感じが良かったです。そして何よりロケーションが良い(それは翌朝解ったことですが)。 4:30起床、外に出ると富士山が飛び込んできました。そして朝焼けに浮かんで極めて印象的。それを見ながらの朝食、この上なく贅沢な食事でした。 天気晴朗なれど風強し、そんな出発時の天候は又、今日のコース決定の選択をどうするかを迫ってきます。 選択したコースは引き返し易老渡に戻ること、聖は今回止めにしました。 帰りは余裕を持って展望を愉しみながら下山、「かぐらの湯」でゆったり汗を流して、早めに帰千したのでした。(9/10~13) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| センジヶ原 | 光小屋 | ||||||||||
  |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| セリバシオガマとダイモンジソウ | ゴゼンタチバナの実 | ギンリョウソウ | ミヤマ オトギリ | ハクサンフウロ | |||||||
  |
 |
 |
 |
||||||||
| トリカブトとアキノキリンソウ | シラネニンジン | オヤマリンドウ | キバナノコマノツメ | ||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ミヤマムラサキ | ヤハズヒコダイ | マイズルソウの実 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
|||||||||||
| 茶臼岳から聖、上河内岳 | |||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 仁 田池 | 易老岳からの光岳 | 下栗の里 | |||||||||
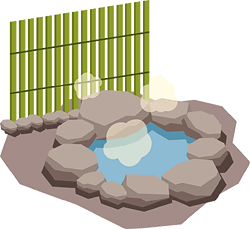 ちょいと歩きに自信を失いかけている今日この頃、西吾妻のリベンジを込めて、ジムのお仲間二人と飯豊の山に挑戦してみました。 ちょいと歩きに自信を失いかけている今日この頃、西吾妻のリベンジを込めて、ジムのお仲間二人と飯豊の山に挑戦してみました。1987年以来となると、なんと30年ぶりの再訪となる。やや、不安に駆られつつの登山である。 今回も川入から。磐越西線山都で降りてBSは?(* ̄0 ̄)/ オゥッ!!ミステーク、バスが運行していない。土日月のみでした。 それを見計らってタクシー運転手が寄ってくる。7000円弱位だよと、しょうがない結局相乗り4人で川入の民宿に乗り付けたのでした。 その集落、今や民宿は2軒のみ、閑散とした佇まいに過疎化の波に喘ぐ姿を垣間見たような気分、ややブルーな気持ちになりました。 その気分、天気まで引き込んだようで、この山行雨、曇り基調のよう、それも有りと思い切り早々に就寝です。 翌朝5:30、宿の4駆で長坂でない近道の栗の沢の登山口に、取り敢えずは最初からのレーンウエア着用無しでの出発となりました。 距離の身近い分、急登が続きます。重荷と蒸し暑さが加わり、ここでも息切れ、小休止を取り仲間に励まされ、登山続行。 7:30、横峯に辿り着けば、後は何とか行ける感じ歩を進めていきます。途中から予想通りに雨がやってきました。 剣ヶ峰の岩稜帯に入る頃には本降りに、慎重に登攀していきます。 10:15頃、三国小屋の庇を借りて小休止、行動食をパクつきます。 撮りたい花は一杯あったのですが、それどころでありません。雨脚がどんどん強くなり風も出てきました。 それでも何回かはシャッターを切ったのですが、ボケボケばっかりでした。 12時前切合小屋に辿り着くも、本日の宿泊予定の本山小屋までは強風の為無理と、引き返してきたグループの見解。 それに従う事にして急遽、切合小屋泊とする。トイレに行くにも難儀する程の暴風雨、まるで台風である。 山小屋での沈も朝日連峰以来久しぶり、ちょっと愉しい気分でもある。ご存知、山自慢で山小屋は溢れかえる。 一晩中、風雨は止まずどのグループも出立思案中、小屋番さんは10時過ぎ雨雲が過ぎ去る見通し、それまで待ったらとの見解、それに従う事にしました。 9時前、雨が小降りになったのを機に出発です。まずは御西小屋を目指し、様子を見て梅花皮小屋を目指すという二段構えで臨みました。 雨であるもののお花は花盛り、やはり飯豊は花のお山、じっくりと観察と云う訳にはいきませんが、目にはしっかりと焼き付けていきます。 姥権現、御秘所を通過、いよいよ本峰へ。風は収まって来たものの、やはり強い。身を低くし体を安定させて一歩一歩山頂ににじり寄る。 11:30、飯豊山到着、遠望は得られなかったものの先ずは山頂を踏め満足、早々に御西小屋を目指します。 ここからは花のプロムナード、草原を風が吹きわたり、花々も揺れながらも、アピールしているよう。 紫系ではタカネマツムシソウが、ミヤマリンドウが、ミヤマトリカブトが、ハクサンシャジンが姸を競ってます。 白系も負けてはいません。 イワイチョウが、マルバコゴメグサが、イワウメが、チングルマ、シラネニンジンが、モミジカラマツが草原の斜面を埋めてます 13:00頃御西小屋通過、明日の工程を考えると梅花皮小屋を目指したほうがベストと判断、更に先に進みます。 乳白色のフィルターがかかりながらも、雪田を背景にした草原は何とも気持が良いものです。 烏帽子岳を超えるのに未だか未だかという感じでしたが、16時半過ぎ梅花皮小屋に到着、この山行の山を越えた感じがしたのでした。 梅花皮小屋は小綺麗ながっちりした2階建て、宿泊者は我がグループ3人だけ、のびのびと宿泊することができました。 寝袋の他に毛布を借りたのだが、それでも寒かった。一足早い秋を感じた一夜でもありました。 最終日、未だ雨は止みません。風も止みません。でも、下山決定、6:50小屋を後にします。 北俣岳から門内岳にかけて風が強く難儀、門内小屋で現況を確認梶川尾根への分岐をしつこく確認、そして梶川尾根の一気の下りに突入しです。 風は止み太陽が出てきました。遥か彼方に飯豊山が見えてます。目を転ずれば麓の集落が小国方面でしょうか、見て取れます。 13時ちょい過ぎ、飯豊山荘に到着、この縦走に終わりを告げたのでした。 お風呂に入ってビールで乾杯、15:25のバスで小国駅へ、その後乗り継いで山形新幹線で帰千、自宅に辿り着いたのが23時頃でありました。 疲れました。リベンジはなったのかな?(8/23∼26) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| マルバコゴメグサ | ハクサンシャジン | アキノキリンソウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| マツムシソウ | エゾシオガマ | ヨツバシオガマ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| アオノツガザクラ | チングルマ | ニッコウキスゲ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 御秘所 | 飯豊本山小屋 | 飯豊山 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ハクサンフウロ | オヤマリンドウ | イイデリンドウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イワショウブ | モミジカラマツ | コバイケイソウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イブキトラノオ | イワオオギ | シナノキンバイ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 梅花皮小屋 | 山深き飯豊連峰 | 梶川尾根から飯豊山本峰を望む | |||||||||
  |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| イワイチョウとヒナウスユキソウ | タカネトリカブト | トモエシオガマ | タマガワホトトギス | ミヤマママコナ | |||||||
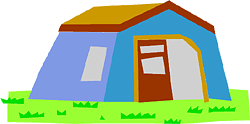 二日目は帰りがけの駄賃のような気分で雄国沼へ、雄国沼せせらぎ探勝路を歩くことにしました。 二日目は帰りがけの駄賃のような気分で雄国沼へ、雄国沼せせらぎ探勝路を歩くことにしました。ただ、雄国沼はシーズンオフ、ニッコウキスゲもレンゲツツジの彩りも無い芦そよぐ湖、そこで雄国山に立ち寄ることに。 ヨツバヒヨドリやアキノキリンソウ等が咲く気持ち良い山道、展望台からの眺めも、ややガスってましたが結構なものでした。 休憩舎でランチ、雄国沼散策路をひと回り、あとは登山口へまっしぐら、ラビスパ裏磐梯へ移動、一風呂浴びます。 汗を流して気分一新、ゴールドラインから磐越道へ。迷走台風5号の北上を気にしつつ南下したのでした。 (8/7) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 雄国沼探勝路入口 | 雄国沼せせらぎ探勝路 | 山ユリと雄国沼と猫魔岳 | |||||||||
  |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| ノギラン/ホタルブクロ | ウツボグサ | オトギリソウ | ギンリョウソウ | コバギボウシ | |||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 雄国山ピーク前の花の路 | 雄国山から雄国沼を望む | クサレダマ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 静かな雄国沼散策路 | |||||||||||
 今週、実は光岳に行く予定だっだのですが、ご存知、さ迷い台風現る!で中止、その代案として突如浮上したのが西吾妻山でした。 今週、実は光岳に行く予定だっだのですが、ご存知、さ迷い台風現る!で中止、その代案として突如浮上したのが西吾妻山でした。折角、山用に空けた時間、兎も角歩ければ良い、台風がより遠くなる東北の山にした訳です。 曇り空も、なんのその、向かうところは天気です、とばかりに5時過ぎ外環へ、そして裏磐梯に向かったのでした。 初め選んだルートは早稲沢登山口からのルート、ところが最初の沢を渡るところで橋が無くて渡渉に躊躇、 というのは、こっちからだとロングコース、9時過ぎからの出発だとタイムオーバーしそう。 方針変更、グランデコスノーリゾートから登ることにしました。 10時過ぎゴンドラ駅到着、もうパノラマゴンドラに乗るしかないです。 と言う訳で10:30山頂駅からスタートです。 スキー場ではヨツバヒヨドリが満開、アサギマダラもそこここで舞っていて、如何にも夏です。 念願の天気は晴れ!が陽が差すと熱いこと、汗ダラダラです。 思ったより手強い急登、コースタイム通りに歩くのでいっぱいいっぱいです。 12時半前西大巓へ。ここで小休止、行動食を口にします。 あと少し、見えてる避難小屋のすぐ横に横たわる山が西吾妻山です。なのに足が進まない、息が上がって、ちょっとまずいな。 行かないことにしました。鞍部でお花を眺めて休息、連れ待っていることにしたのです。 脱水症状かなぁー、それともステント留置中の体には過酷すぎるのかなぁ~。 14:20過ぎ連れが戻てくるまでノンビリ、東吾妻山にガスが掛かってきました。 さて、一気に下ります。ゴンドラの最終時刻は4:00、それに間に合わなければなりません。 気分は平常に、ただ、ちょっと心が悩ましい、自分だけが、以前、踏んでいるとはいえ、頂上を踏まなかったのだから。 これから、こんなの事が多くなるのかなぁ~。 今日のお泊まりはペンションベイクドポテト、その夜はちょいと輾転反側、熟睡感の乏しい朝ではありました。(8/6) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| スキー場斜面はヨツバヒヨドリやハハコグサの花盛り | 小野川湖かな? | 稜線に出ると東吾妻山の穏やかな姿が | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イワイチョウとアサギマダラ | ヤマハハコ | ミヤマリンドウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イワイチョウ | ネバリノギラン | ホソバノキソチドリ? | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| スキー場では植栽かヤナギランが | ネバリノギランのアップ | ホツツジ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| シナノオトギリ | 西大巓 | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ハクサンシャジンが印象的 | ミヤマアキノキリンソウ | シラネニンジン | |||||||||
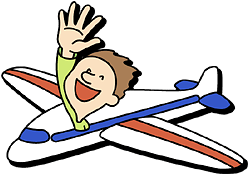 夏山シーズン到来、幌尻岳目指して、文字通り飛んできました。 夏山シーズン到来、幌尻岳目指して、文字通り飛んできました。と言って前から綿密な計画を立ててた訳ではないのですが、グットタイミングのお誘い、簡単に行ける所でないので、便乗しました。 前日、麓の豊糠のペンション「くまさん荘」に入り、「とよぬか山荘」7:00発のシャトルバスで入山です。 22㎞弱の林道を1時間弱でバスはガタゴト走ります。林道第二ゲートが終点下車、ここからさらに続く林道を歩き始めます。 長~いダラダラ坂道、重い荷を背負ってかなり頑張ったのですが、なかなか時間の短縮はできません。 ややコースタイムより速い程度で北海道電力取水施設へ。そしてここから本番、靴を履き替え、額平川に沿って歩いていきます。 そして渡渉開始、ジグザグに幾度も渡渉を繰り返して行くのですが、慣れないこと、かなり緊張します。 額平川の今回の水深は総じて膝下位、水流も大胆に渡ればこなす事が出来、前日雨が降った割には、何とか遡行できラッキーでした。 12時ちょい過ぎ、幌尻山荘に到着、小屋番さんが11時までに到着した人だけに、そのまま幌尻岳登山を許可するとの事、今日は無理の様です。 体力温存、明日に備えます。 半日、食事を作りながら、他の登山者たちと情報交換しながら、そして時間を持て余しながら、過ごします。 そして、翌朝、夜明けと同時に山小屋は蠢き出します。我々もその流れに乗り小屋外へ、今日は晴天、出発進行、頃は4:50でした。 寝起き直ぐの急登、樹林帯の中の清々しい道を一歩一歩こなしていきます。 路脇にはズダヤクシュ、アリドウシラン、エゾノヨツバムグラ…自己主張しています。 命の水分岐点辺りで水休憩、ここから更なる急登が始まります。 稜線に張り付くハイマツの下にゴゼンタチバナにリンネソウが花をつけておりました。ここで会えるとは感激です。 展望がきくとまず目につくのが戸蔦別岳の三角錐、そして眼下に広がる北カール、その淵を回り込んで山頂を目指す。 おぉ~、お花畑は百花繚乱、すごいの一言です。印象的な花を書き連ねて、先に進みましょう。 深紅のエゾツツジ、ハクサンチドリ、紺碧の空にも負けないエゾヒメクワガタ、ミヤマリンドウそしてチシマギキョウ、紺碧の空に映えるはチングルマにハクサンイチゲ・・・ときりがありません。 そして幌尻岳山頂に到着、360度の展望、日高の山並みが広がりが圧倒的です。遥か北の雲間には大雪の山々が顔を出しておりました。 展望を充分に愉しんだら、一気に下ることにしましょう、5時のシャトルバス乗らなければ。 天候に恵まれ、無事、もう一泊お世話になる「くまさん荘」にたどり着いたのでした。(7/23~26) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 渡渉を繰り返す | 幌尻山荘 | エゾノトウウチソウ | |||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| リンネソウ | ?ナズナ | ギンリョウソウ | ミヤマトウバナ | オオバノヨツバムグラ | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| ミヤマダイコンソウ | ユキバヒコダイ | オククルマムグラ | アキノキリンソウ | ゴゼンタチバナ | |||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ハクサンイチゲ | サマニヨモギ | ハクサンチドリ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| キバナシャクナゲ | ムカゴトラノオ | カラフトイチヤクソウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| エゾツツジとエゾヒメクワガタ | エゾフウロ、チングルマ、ウサギギク… | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| エゾノツガザクラ | アオノツガザクラ | ウコンウツギ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| チシマギキョウ | ミヤマリンドウ | イワブクロ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| エゾコザクラ | チングルマ | ||||||||||
 祇園祭に行ってきました。 祇園祭に行ってきました。うん十年振り、ちょいとワクワク。 5時頃、阪急四条烏丸駅から地上に顔を出すと、正に祭りの喧騒の中、予想していたものの覚悟がいりそうです。 兎も角、人の流れに身を任せることにしました。 烏丸通を上がり錦小路通に、その辺りをウロウロ、一度四条通出て、早めの夕食、生ビールが美味かった。 喧騒を逃れてのひと時、たまりません。 さて、街中へ。陽が落ちて夕間暮れ、祭り提灯の灯りが増し、賑やかさも佳境に入ってきました。 薙刀鉾から、函谷鉾、菊水鉾、放下鉾へ。 もちろん、山も巡ります。楽しいのは太子山と岩戸山。 子供達の粽売りの囃子言葉、「常は出ません、今晩限り♫~…ちまきどうですか~」 鶏鉾まで来た頃には8時半頃、疲れました、今日はこの辺で帰ることにしました。(7/15) そして山鉾巡行の日、9時スタート、その2時間前に行って場所どりするのが常識などだとか。折角です、やりましょう。 薙刀鉾の様子を伺って、ちょいと朝食を。そして「くじ改め」が行われる交差点に陣取ります。 ここでの各鉾、各山の正使、副使の市長への挨拶、各々の正使のパフォーマンスが楽しめ、飽きさせません。 薙刀鉾から舟鉾まで、9時から11時までの華麗なるショーでありました。(7/17) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 薙刀鉾 | 菊水鉾 | 鶏鉾 | |||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
| 孟宗山 | 占出山 | 霰天神山 | 伯牙山 | 放下鉾 | 月鉾 | ||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
| 芦苅山 | 油天神山 | 太子山 | 岩戸山 | 白楽天山 | |||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 薙刀鉾 | 占出山 | 孟宗山 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 霰天神 | 四条傘鉾 | 綾傘鉾 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 菊水鉾 | 放下鉾 | 岩戸山 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 函谷鉾 | 郭巨山 | 舟鉾 | |||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
| 占出山 | 木賊山 | 伯牙山 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 保唱山 | ||||||
 今日は七夕、とは関係ないのですが、リンネソウを見たいという、野草教室のお仲間と池の平湿原に行ってきました。 今日は七夕、とは関係ないのですが、リンネソウを見たいという、野草教室のお仲間と池の平湿原に行ってきました。なので、左程特筆すべき話はないのですが、今の季節の池の平湿原のご報告ということで載っけてみました。 その前に、九州の豪雨被害、心痛みます。 英彦山の周囲、筑後川流域は古代日本の心臓部、巡った所も多く景観を思い出します。心の中で再起のエールを送ります。 そんな訳で、自己中の写真の羅列といった具合ですが、それも何時もの事、軽くスルーしてください。 目的のリンネソウ、まだ蕾でした。ただ薄赤紫の蕾は1週間後にお出でと言っているようでした。 白馬の大池の淵で見たときはわかり易かったのに今回は苦労しました。 イチヨウランに出会えたのも、やって来た成果でしょうか。全体としてはアヤメの季節という感じでした。 足元はグンバイズルが花盛り、連れの方が大喜びでありました。(7/7) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| アヤメは今が盛り | ハルカラマツ | その足元にはグンバイズル | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| オオヤマフスマ | ミヤマウラジロイチゴ | ミヤマニガイチゴ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ゴゼンタチバナ | ツマトリソウ | イワカガミ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ハクサンシャクナゲ | マイズルソウの季節でもあります | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| クモキリソウ | テガタチドリ | ハクサンチドリ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ハクサンフウロ | グンナイフウロ | ヤマオダマキ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 三方ヶ峰の花形コマクサ | そしてオンタデ | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イチヨウラン | 未だ蕾、リンネソウ | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| オトギリソウ | スズラン | ベニバナイチヤクソウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 池の平湿原 | シャジクソウ | レンゲツツジ | |||||||||
 今年の梅雨はどんな様相を見せるのでしょうか。 今年の梅雨はどんな様相を見せるのでしょうか。今のところは空梅雨、おっとどっこい、スパコンの世界、人はじっとやり過ごすしかありません。 そんな時、晴れ間を縫って行くには好都合な情報(6/7)が、草津白根山の火山情報、噴火警戒レベル1になったという。 いきましょう!というお誘いに、即是、久しぶりの草津白根山を楽しんできました。 ネックは遠いこと、往復8時間以上要してしまう。 それも良いかと早朝発、鬼押し出し・万座ハイウェイを奮発、9時頃湯釜Pを出立したのでした。 ワタスゲが白の小穂が目立つ弓池を巡り、コマクサ・リフトへ。リフトの横をノンビリと登り始めます。 足元にはミツバオオレン、イワナシの花が目立ちます。ショウジョウバカマの花もあったりして嬉しがらせます。 マイズルソウの花は未だ、もうちょっとですね。 間もなく、中央火口の望める場所に。なかなか壮観です。以前、来た時にはガスの中、この印象がありませんでした。 その意味でも今日の登山は良いアイデアでした。 火口の周囲を巡る遊歩道を、正に散策。大切に保護、育てられているコマクサが遊歩道の周りに一杯。 只、花期はこれから、ツボミは多く見かけるのですが・・・、見頃は7月に入ってからでしょうかね。ミネズオウも少し花を付けておりました。 ハイキングマップ通り、遊歩道最高地点まで歩いて、奥志賀の横手山や笠ヶ岳を眺め、本白根展望所へ。 そして、道なりに鏡池方向へ向かいます。道脇にはコイワカガミが道を彩って、登山者に望外の喜びを与えてくれます。 コイワカガミに混じってミツバオオレンに変わりツマトリソウを多く見かけます。ゴゼンタチバナも仲間入り。 ツバメオモトを発見、なかなか楽しい道です。 ロープウェイ山頂駅に着いて一回り、トイレを借りつつ、ここでランチとしましょう。 舗装道路を湯釜Pまで戻り、ちょっと湯釜見物。この周辺が規制対象の中心でした。 今日は芳ヶ平へ足を延ばすことは止め、草津の湯に浸かって、ゆっくり帰ることにしましょう。(6/23) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| R292脇はすでに天空の庭、ワタスゲが揺れています | |||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イワナシ | ショウジョウバカマ | ミツバオオレン | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 不意に姿を現した中央火口 | 火口原 | 奥志賀・横手山後ろに岩菅山 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 貴重な一輪コマクサ | ミネズオウ | アカモノ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| コイワカガミ | 湯釜 | マイズルソウ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ツバメオモト | ツマトリソウ | ゴゼンタチバナ | |||||||||
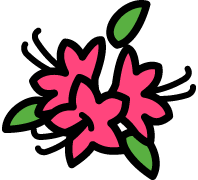 梅雨入り前の晴れた日は貴重です。それも日長の今の時期は。 梅雨入り前の晴れた日は貴重です。それも日長の今の時期は。そんな時、前日光の禅頂道歩きのお誘い、ピッタリのコース、乗ることにしました。 朝一の電車を乗り継ぎ東武日光駅へ。お金節約より時間節約が優先、中禅寺湖までタクシーを駆り半月山登山口へ。 即、登山開始です。薄々感じてはいたのですが、やはりツツジのシーズンは終わっているようです。 ちょっと残念、それでも咲き残りを愉しみながら、何より新緑の美しさに魅せられながら歩くことにしましょう。 まずは茶ノ木平を目指します。ここでミス、うっかり通過明智平への分岐を通過、半月峠での分岐と思い込んでいたためです。 が、林道に突き当たって、さっきの分岐しかないと気付き、戻るタイムロスを初っ端から犯してしまいました。 ま、足慣し足慣し。第二展望台で男体山と日光白根山を望め、良いアクセントになりました。 気を取り直して再出発、細尾峠を目指します。足下は笹原、野草観察には適さないようだ。 でも、森を覆いつくす新緑、それだけで大満足です。所々でシロヤシオ、ミツバツツジ、ヤマツツジの花がアクセントを付けます。 細尾峠を越え、いよいよ薬師岳へ。所々に石の祠が点在、禅頂道の痕跡に行き当たり、行道に勤しんでいる気分になってきます。 清々しい気持ちで薬師岳、夕日岳、地蔵岳と踏んで、ハガタテ平の分岐点へ。 ここからは薄暗い植林帯の沢沿いの道を一気に小峰神社へくだります。 少し花に飢えたこの山行にサプライズがあったのです。クリンソウの群落に突然、バッタリ出会ったのです。 8時間のロングトレイルのご褒美に拍手喝采、皆の疲れも吹き飛びました。 そして、古峰原神社BSの無事到着、最終バスにのりこんだのでした。 (因みにバス乗客は我々だけ、禅頂道でも誰にも出会いませんでした) (6/5) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 茶ノ木平分岐 | 茶ノ木平 | 第二展望台から | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| わずかにシャクナゲ | シロヤシオ | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 細尾峠への分岐 | 新緑が眩しい | 細尾峠 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 薬師岳 | お不動さん | 夕日岳 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ヤマツツジ、 新緑に映えてました | ドウダンツツジ | 地蔵さん | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| クリンソウの群落出会えてハッピー | コンロンソウ、君に出会えて嬉しいよ | ||||||||||
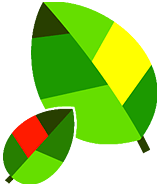 躑躅の便りが其処此処に飛び交っている。 躑躅の便りが其処此処に飛び交っている。家の周りの園芸系のツツジも次々と咲き出し、取り敢えずは腰を上げねばと出掛けた訳です。 さて、何処へ。ここの所お馴染みの浦山大日堂をベースに大平山に様子を見に行くのも良いかなと考えたのでした。 咲いてなくても、新緑が楽しめるはずです。福寿草の季節が終われば静かな山登りが楽しめるはずです。 BS側に車を一泊させてもらって、トイレを済ませ7時半頃出発です。 大日堂で山での安全を祈願してから、地蔵峠を目指して歩き出します。 足下にはヒメレンゲ、 ムラサキケマン、キケマン、マムシグサ等見送ってくれます。 細久保集落への道端にはヤマクワガタやジュウニヒトエも。 地蔵峠を越え、新秩父線の高圧鉄塔に着くと取り頃のワラビが一杯、好きな人には堪らないだろうなぁ。 さて、ドンドン行きましょう。新緑が素晴らしい。2ヶ月前とは雲泥の差、もうカラ沢を見渡すことはでき無いほど、緑が覆いつくしています。 大ドッケ辺りでひーひーフーフー、シュラフと水を背負っているかなぁー、ここで一服です。 更に上に分け入ります。この辺からガスが立ち込めてきました。もうちょっとお天気持つと思ったのになぁ。 大平山辺りで林道が錯綜、路を見失うがここは直登、山頂に。残念ながら早すぎ、ツツジは蕾のまま、やっぱり6月10日頃かな。 留まるには天気が悪すぎ歩みを進め長沢背稜縦走路に合流します。気持ちも少し沈み気味もう休みたいと酉谷避難小屋を目指したのでした。 辿り着いたのが14時頃、温かいワンタンを食べましょう。切り餅を焼いて、餅入りワンタン、中々イケますよ。 そうそう、小屋前に新たな水場が作られていました。ありがたいことです。大切に守られると良いですね。 今日はここでノンビリ、次の来訪者を待ちましょう。が、本日の来訪者は自分以外零、少し寂しかったです。 そう言えば、前回は2年前の秋、その時は夕方遅くに鹿調査の2人がやって来たのになぁ。 今日は本を持参してこなかったので、ラジオの友に。 18時には寝袋に入ってしまったので、深夜に目が覚めてうつらうつら、しっかりラジオ深夜便を聞いてしまいました。 翌朝、予想通り雨模様。目覚ましのホットコーヒーを飲みながら出立の準備をします。 取り敢えず、空荷で酉谷山へ。どうもこの山では好天に恵まれません。 小屋に戻って再出発、後は下るだけ、ガスの中、目は道端に注がれます。 タチツボスミレが一杯、長沢背稜はスミレロードになっています。所々にエイザンスミレやフモトスミレも。 マイズルソウが一斉に葉を茂らせ間もなく花付けそう。そうすると梅雨の訪れを思い起こしてしまいそう。 ワチガイソウやミツバツチグリも健気に咲いておりました。 名残りのアカヤシオも見ることが出来ました。 三ッドッケに寄って仙元峠へ。ここで早めのランチを取って、後は一気に下りるだけ、14時前に裏山大日堂に辿り着いたのでした。(5/16.17) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 浦山大日堂 | 地蔵峠 | 高圧鉄塔下のワラビ | |||||||||
 |
 |
 |
 |
||||||||
| タチツボスミレ | 新緑の峠の尾根 | ジュウニヒトエ | マムシグサ | ||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| フモトスミレ | エイザンスミレ | ヤマクワガタ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 大ドッケ | 大平山 | 霧中のオオカメノキ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 早朝の酉谷小屋からの眺め | 酉谷山 | 仙元峠 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 名残りのアカヤシオ | 落花 | 長沢背稜の一コマ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ワチガイソウ | ミツバツチグリ | 蕾のマイズルソウ | |||||||||
 スミレ咲く季節、鉄五郎新道のイワウチワも咲き出したという。 スミレ咲く季節、鉄五郎新道のイワウチワも咲き出したという。やはり、おめもじ願わないと春の区切りがつかない感じ、3年ぶりかなぁ。 という事で外環道、関越道、圏央道と乗り継いで寸庭を目指します。 青梅ICを下りる。青梅は今が桜満開、春真っ盛りでした。こちらの気持ちも何故か浮き立ちます。 やはり、桜には魔物が潜んでいるのかもしれません。 ならば、通り道の金剛院の枝垂桜を見ていく事にします。 予想通りの美しい枝垂桜でした。 気分を良くして寸庭へ。私のお気に入りPです。 取り敢えず大塚山を目指します。家の庭々でも春の花が競演、桜は勿論、ハナモモがレンギョウがユキヤナギがボケが・・・大賑わいです。 寸庭川にかかる小橋を渡り鉄五郎新道を目指すのですが、手前の枝尾根が目に入ってしまったのが運の尽き、 そちらをアタックしたくなってしまいました。 結果、四苦八苦の直登、辿り着いた所が広沢山でした。成る程ここにでるんだ。 取り敢えず大塚山まで行ってから、広沢山まで戻り、別の下山路をくだります。そう!これが鉄五郎新道です。 下っていくと間もなくイワウチワの群生地です。 咲いておりました。ただ、何と無く以前より薄い感じ。やっぱりオーバーユースなのかな。 確かに三々五々お花目当ての登山客がやってきます。実際、40名のイワウチワツアーの団体さんともすれ違いました。 悩ましいところです。 イワウチワも良かったですが、ミツバツツジも咲き出し、沢山のスミレ達にも出会え嬉しさてんこ盛り、兎も角愉しい春の花探しの山歩きとなりました。そして、昼過ぎには下山、余裕を持って家路につくことができたのでした。(4/13) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 金剛院 | |||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| イワウチワ三態 | |||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ナガバノスミレサイシン | コミヤマスミレ | ヒカゲスミレ | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ヒナスミレ | ヤマエンゴサクとルリシジミ | ミツバツツジが咲き出した | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| シロバナエンレイソウ | ハナネコノメ少し残ってました | ツルネコノメ | |||||||||
 予定通り、5日午後4時頃大雲沢ヒュッテに到着、お風呂で出迎え、嬉しいですね。 予定通り、5日午後4時頃大雲沢ヒュッテに到着、お風呂で出迎え、嬉しいですね。そして夕食、明日の守門岳登山の事簡単な打ち合わせを済ませます。 翌日の天気を気にしつつ、ちょっと胸ドキドキさせながらの就寝となりました。 翌朝、おぉ~快晴、午前中は持ちそう、胸ワクワクである。 今回はヒュッテのご主人に同行をお願い、6:30大原スキー場をスタートしたのです。 守門岳に連なる尾根に朝陽があたり、行く手に立ちはだかるように光り輝いています。 スキー場の最上部のリフト乗り場まで歩を進め、650㍍ポイント辺りでそれぞれワカンジキなりスノーシューに履き替えて尾根状の林に突入です。 右手の上祝沢辺りで雪崩の痕跡、デブリが見て取れます。そうした危険があるので夏道は辿らず迂回するようです。 ただ、このコース、2か所ほど急斜面を越えなければなりませんでした。ご主人のガイドでなんとかクリア、細心の注意力が要求されました。 今年は雪が一度解けて、その上に新雪が積もった故、非常に歩きにくい状態になっているとの事、冷や汗ものでした。 なんとか1100㍍の稜線上に這い上がると、それからは快適な白銀の稜線漫歩が待っていました。 白く嫋やかな峰が目指す守門岳に向かって続いています。 そして、所々に大きく雪庇が張り出しています。その雪庇の上に出て、雪庇上を慎重にゆっくりと歩を進めていきます。 山スキーを楽しむペアが姿を見せたかと思う間もなく、我々カンジキ隊をすんなりと追い越していきます。早いな体力あるとなぁ、見送るばかりでした。 気を持ち直して、鈍足隊はひたすら一歩一歩歩を進めるだけです。 その合間に、目を転ずれば、毛猛山塊を始め雪の奥只見の山々が360度展開!その様は何物にも代えがたいものでした。 1348㍍付近のなだらかな部分で小休止、1537㍍山頂に着いたのが12:00頃でありました。 天気が下り坂、お日様は姿を隠し、風が強くなってきました。 早々に証拠写真をとって撤収、少し余裕が出てきてその一大パノラマを愉しみながらの下山です。 先ほどの休憩ポイントでランチ、宿のおにぎりをポットのお茶と共に流し込みます。 20分程のランチタイムのあと下山開始です。 難所は2か所の急斜面、幾度かずり落ちながらも宿のご主人の跡を忠実にトレースして、無事スキー場に辿り着いたのでありました。 起点の宿に着いたのが16:00頃、経過時間9時間半の春山登山でした。 皆さん、私もお疲れ様、宿のご主人さまありがとうございました。(4/6) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
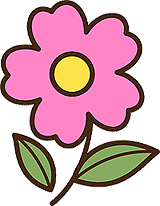 桜週間となっている南関東に背を向けて新潟へ。 桜週間となっている南関東に背を向けて新潟へ。雪踏みをしてみたくなったのです。 春の残雪登山と言えば守門岳が真っ先に思い浮かび、即計画、お仲間二人を誘って実行と相成りました。 その道すがら、あまり天気が良いので、ちょっくら寄り道六万騎山へ。 坂戸山をみても雪が残っていて、あまり期待しないで訪ねたのでした。 が、案に相違して、初っ端から艶やかなミスミソウ(ユキワリソウ)が迎えてくれました。昨年の能登半島の猿山岬を思いだします。 それぞれに個性的で艶やかである。 キクザキイチゲも妍を競っています。おやおやコシノコバイモおりました。そばのスミレさんは毛が多くて丸葉、アオイスミレでしょうか。 そして、看板娘カタクリの花も咲いておりました。 幸先良い出だしに興奮!地蔵堂の石垣に腰を下ろして日向ぼっこしながらのランチ、極上の時間です。 そして、いい気分で明日の守門岳の前進基地、大白川の大原スキー場に向かったのでした。(4/5) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 地蔵堂 | 魚沼平野 | 六万騎城址 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ミスミソウ四態 | |||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| キクザキイチゲ | 後ろ姿 のカタクリ | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| コシノコバイモ | アオイスミレ | カタクリの群生 | |||||||||
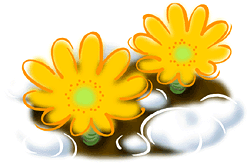 ‘暑さ寒さも彼岸まで’春の兆しに会いに出かけてきました。 ‘暑さ寒さも彼岸まで’春の兆しに会いに出かけてきました。大ドッケの福寿草に。 実は4日前18日に挑戦したのですが、沢に下る所で分からなくなって、しょうがないと一気に尾根道に這い上がることにしました。 そこから大ドッケを目指し、福寿草自生地に下ろうと思ったのですが、途中で気持ちが萎えちゃって地蔵峠にくだったのでした。 なので、今日22日はリベンジと言う訳です。 幸い、今日は大日堂用の駐車場が空いていたので置かせていただき、8時半サクサクと出発します。 素直に道なりに進めばよかったのです。つまり「松浦本」を良く読み込めば間違うことも無かったのでした。 上を目指さないで、不安定な斜面を左に巻いて沢に降り立ち、前方の支尾根を乗越し、その沢を上へ上へと詰めていきます。 石ゴロの沢をエッチラオッチラ、息が上がり、まだ~と弱音が出る頃、やっと目的地に到着しました。 なるほど、斜面に福寿草の大群落が広がっておりました。 実際、その場に立ち、春の陽光をパラボラアンテナのように受け、黄金に輝く福寿草を目にすると、改めて訪れてよかったと思うZIOめでありました。 そして、自身を含め、この地を訪れたいと思うのは至極当然のように思われます。と同時に荒れない様にする知恵を出し合いたいものです。 心ゆくまで眺め、軽くランチをとってから、大ドッケの尾根にとりつきます。 前日、雪が意外と積もったようで、大平山に続く尾根道は膝頭辺りまで吹き溜まりがあり、ちょいとワクワク、 念の為、アイゼンを装着、一気に地蔵峠を目指して下りました。地蔵峠でアイゼンを外し、無事2時半頃大日堂に帰ってきたのでした。 (3/22) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| カラ沢沿いの路 | カラ沢を遡上 | 福寿草群落まもなく | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
 |
|||||||||||
 |
 |
  |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 1315峰付近 | 峠ノ尾根 | 地蔵峠 | |||||||||
 遅ればせながら鷹ノ巣山へ行ってきました。 遅ればせながら鷹ノ巣山へ行ってきました。皆の山報告を見ながら、あったかい所でヌクヌク・ハイキングもちょいと心苦しい、行って見ますかと腰を上げた次第です。 今回もジムのお友達とサクサク登山、こんな感じでした。 奥多摩湖畔に8時頃到着、トイレを済ませ出発進行、オーソドックスに水根沢沿いを遡行します。 先日の春一番の陽気で雪はないだろうなと思いつつも、少しは欲しかったもと、勝手な都合を思い描きながら歩みを進めます。 日影部分には薄っすらと昨夜の雪の跡が残っていて、乾燥した枯れ葉路と交互に現われます。 水根沢が尽き、榧ノ木尾根に取り付く辺りから枯れ葉の下が氷結、すべりやすく歩きずらくなる。 適当な場所でアイゼン装着、無理せず確実に一歩を刻んでいく事にします。 そして縦走路に出れば、後は展望を愉しみながらピークを目指すだけ、疲れた体に甦ってきます。 尾根道は雪がほとんど無くなり泥濘の路が続きます。それでもエッチラオッチラ、鷹ノ巣山山頂に辿り着きます。 おぉ、素晴らしき展望、前景に奥多摩三山(大岳山・御前山・三頭山)、奥に丹沢山塊、 その上に屹立する富士山、目を転ずれば南アルプスの白き峰々が飛び込んできました。 そうです、これが見たくてやって来たのでした。 そんな至福の一刻も、風が強くランチ場所には適しません。 風の当たらない場所を求めて、そそくさと頂上を去ります。肩の穏やかな場所を選んで、待望の熱々即席めんを頂きます。 これまた最高!なんで山で食べるラーメンはこんなに美味しいんだろう。 あまりゆっくりはしていられません。石尾根歩きを楽しんで六つ石山経由で下りることにします。 雪道と泥道が交互に現れる快適とはいいがたい路でしたが、愉しい路でした。 六つ石山までくれば、後は一気に下るだけ、陽光残る内に多摩湖畔に辿り着けたのは何よりでありました。 時間は既に5時、一路帰宅の途についたのでした。(2/19) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 水根沢を行く | 縦走路へ鷹ノ巣山は目前 | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 鷹ノ巣山 | ご存知!富士山 | 南アルプス遠望 | |||||||||
 |
 |
||||||||||
| 石尾根を行く | 奥多摩三山と冨士 | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 将門馬場辺りのブナ・ミズナラ林 | 六つ石山北斜面 | 小河内ダム | |||||||||
 低山徘徊が続きます。 低山徘徊が続きます。今回は筑波山、足慣らしに手軽な何所かというリクエストに答えての選択でした。 筑波山だと片道70㎞以内、高速道路使用しなくてもよい距離、我が家からは好立地なのです。 混雑する表参道は避けて、真壁町の薬王院口から登ることにしました。 溜池つくし湖の周辺の駐車場に車を置いて出発進行。 観光ミカン園をの中通っていきます。このミカン園、北限のミカン園とか。 ミカンの収穫期は終わったらしいけど、取り残しがチラホラ、道端ではホトケノザも初々しい花をつけている。 今日は晴れ、風邪も穏か、光の春に相応しいコースである。 その路をしばらく進むと登山道の入口に辿り着きます。 そこからは一直線、一気に標高を上げて行きます。木の階段が現われます。これが思いの外難敵、延々と続く感じで一気に登るとさすがに息がゼイゼイ、水を補給して呼吸を整えます。 ただ、此処まで来ると後は楽勝、気持ちにゆとりを感じてゆったりと登っていきます。 間もなく自然研究周回路の分岐に到着、右回りで山頂を目指します。 途中の岩場が絶好の展望台、暫し俯瞰を愉しみ、まずは男体山神社にお参り、ついで女体山神社にお参り、そして御幸ヶ原でランチとしました。 風が出てきて、やや落ち着かないランチ風景となってしまいました。それでも熱々のカップ麺は何よりのご馳走、至福のひと時でありました。 と言っても風は止みそうもない、とっとと下りることにしましょう。 下り口は筑波ユースホステル跡へ、その付近、カタクリの群生地らしいのでその下見も兼ねて。 辿って見ると、作業用道路にもなっているようで、面白みのないみちでした。カタクリの花の咲く頃、どんな変化を見せるか楽しみでもありますが。 林道をぐるっと回り、朝来た薬王院口に下ります。 宝篋印塔等が見えてくるとお寺の境内、瀟洒な三重塔が姿を現します。 池に宝船のように雛人形の乗った小舟が。そうか、ここは真壁町、町おこし雛祭りイベントはつとに知られていました。 境内を一回りし、スダジイの巨木に感出発点嘆して、つくし湖に戻ったのでした。(2/6) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| ミカン畑 | 光に向かってホトケノザ | 登山口入口 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 自然研究路 | 石(磐)への信仰を垣間見る | 男体山もま近 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 富士山は雲の中スカイツリーや高層ビル群が | 女体山望む | 女体山山頂 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 真壁の雛祭りイベントの一環か | 椎尾山薬王院 | スダジイの巨木 | |||||||||
 笑ってしまいます。 笑ってしまいます。今年、今月三度目の三浦半島訪問となってしまいました。 二度、三浦アルプスを目指して失敗(何と大層なアルプスである事か)、今回はそんな訳にはいきません。 京急田浦駅に7時半頃到着、もう慣れた道筋、迷うことはありません。 キグナス石油のGSの角を曲がり住宅地を登りつめ鉄塔の立つ眼前の丘陵に取り付く。鉄塔保守の為の階段路のよう。 尾根に辿り着けば、高圧鉄塔に沿うように乳頭山へ。先週見た光景が広がります。何回見ても良い感じです。 さて、乳頭山から南尾根をコースに取ります。 最初、ちょこっと富士山を拝めますが、後は常緑広葉樹や竹藪に囲まれて展望はさっぱりです。 観音塚までけっこうアップダウンがあって、それはそれで愉しい。 観音塚からが、今日のハイライト。仙元山でピークに達します。相模湾越しに見るヨットと江の島と富士山、最高ですね。 ランチする前に下りてきてしまったので、通り沿いラーメン屋さんで、文字通りランチ。 そしてここから本日の第二目標、長柄桜山古墳群を訪ねたのでした。(1/26) |
|||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 三浦アルプス取り付き口 | 乳頭山へ | 横須賀港 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 相模湾越しに見える富士山 | タブの木の並木 | 観音塚の石仏 | |||||||||
 |
|||||||||||
| 仙元山からの展望 | |||||||||||
| あけましておめでとうございます。 2017年が始まりました。皆様はどんなお正月を迎えられたのでしょうか。 好天に恵まれ、まずは何よりのスタートになったのではないでしょうか。 昨年末、突然、白内障の手術を受けることを決め、半月ほど出かけるのを自重しておりました。 その自らの諫めを解く日を1月1日と決めておりました。 そんなこんなで、朝一番のバスに乗りスタートです。目指すは三浦アルプス。 JR、京急を乗り継ぎ、京急田浦に8時半頃到着、紺碧の空、勇んであるきだします。 が、?登山口を探してウロウロ、兎に角尾根に登って見れば見えてくると、住宅地の坂を登っていきます。 この辺り、平地が少ないためか丘の上まで家が立ち並び路地が縦横無尽、鷹取山ハイキングコースの案内だけが妙に目に入ります。 その内、こんな考えが。鷹取山に針路をとって、そこから尾根伝いに三浦アルプスに合流する道を探そうと。 そんな経緯は置いとけば、この坂道、いいですね。軍港横須賀を眺めが格別、植栽された柑橘が実を付け彩を添えます。 間もなく、石切り場のような地点に、ここが鷹取山。 鷹取石として珍重され大いに利用されたらしい。その先に展望台が作られ山頂(139㍍)にもなっている。 その展望は見事でした。眼前に横須賀の街並みが広がりその先に軍港横須賀港と東京湾が、目を転ずれば富士山が相模湾越しに見えます。 展望を愉しんだら神武寺に向かいます。本当は三浦アルプスへ繫がるルートを探すはずでしたが変更、ハイキングルートに導かれた訳です。 初め、ちょっとした鎖場、愉しませてくれます。その後は広葉樹林の中をいきます。房総の山と同じ風景、環境が似ているがよく解ります。 神武寺が見えてきました。予定外の訪問です。初詣と言う訳です。薬師堂で健康を願いました。 ここで岩隙植物群落を目にする。海底の隆起による堆積岩の露出面の今の表情である。良いものを見ました。 此処で東逗子駅辺りに下ります。そこから二子山への登り口を見つけとりつきます。 ここで、またウロウロ。今度は古墳探し。長柄桜山古墳群がこの辺りの分譲宅地周辺にあるはず、そこに寄って行こうと考えたからです。 だが、見つからず諦めて二子山ハイキングコースに復帰、二子山で展望を愉しむことが出来ました。 (長柄桜山古墳群は場所特定が間違っていて、無い所を探し回っていたわけです。古墳探しは次回に、欲張りました) 南郷上ノ山公園へ下り、丁度出会った路線バスでJR逗子駅に戻ったのでした。(1/1) |
|||||||||||
 |
 |
||||||||||
| 鷹取山からの横須賀港 | 鷹取山山頂展望台 | ||||||||||
 |
 |
||||||||||
| 鷹取山からの富士山 | 石切り場と横須賀港 | ||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 神武寺 | ?観音と六地蔵 | 岩隙植物群落 | |||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 東逗子駅付近からの富士山 | ヤツデの花 | 二子山から展望 | |||||||||
 |
|||||||||||